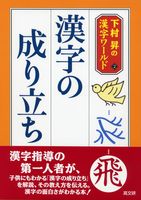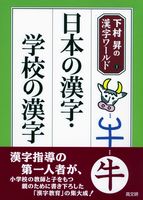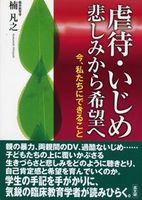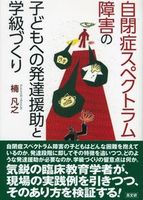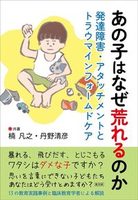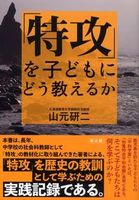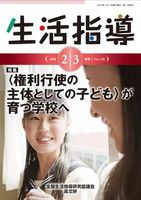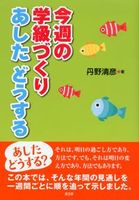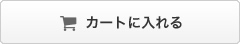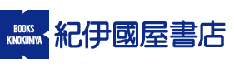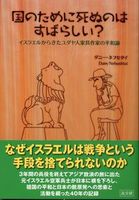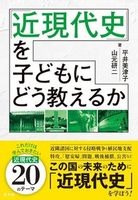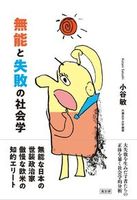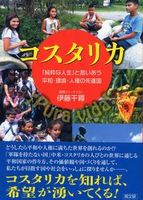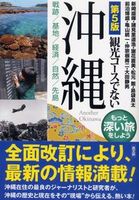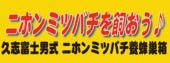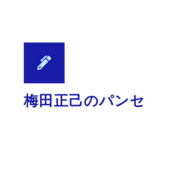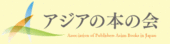アジア新風土記(98)フィリピン前大統領の「罪」 - 2025.03.31
生きている漢字・死んでいる漢字
下村昇の漢字ワールド④
| 著者 | 下村 昇 著 |
|---|---|
| ジャンル | 教育書 > 教育 |
| シリーズ | 下村昇の漢字ワールド |
| 出版年月日 | 2006/03/10 |
| ISBN | 9784874983584 |
| 判型・ページ数 | A5・170ページ |
| 定価 | 本体1,600円+税 |
| 在庫 | 在庫あり |
1「読み」は理解活動「書き」は表現活動
*「空っぽ」も「足す」も読めない
*教科書以外の図書の役割
*ある編集者との会話
*「書く力」は「読む力」の半分
*より積極的な訓練が必要
2学年配当漢字にこだわる教科書や児童用図書
*なぜ、ひらがなから教えるか
*読んでわかるということ
*子供の本までひらがなが多い
*ひらがな表記の本でどんな子が育つのか
3書けない漢字は、生活から離れた「死んでいる=身についていない」言葉
*「玉」は書けても「ギョク」は書けない
*漢字の指導は言葉の指導
*漢字を教えるときの注意と対策
*教師の誤った漢字観
4悪しきもの、熟語の交ぜ書き表記
*読み書き教育の原則は
*新出漢字の読みは「音」か「訓」か
*あるネットから
*新聞社の言い分
*漢字は表語文字
5熟語の意味は熟語で理解する
*日本語になりきった熟語
*言葉の認識のさせ方
*漢字指導を阻害するもの
*言葉(漢字)の教え方例
*「読み書き同時学習」は避ける
第二章 かなの学習と漢字の学習
1かなの学習
*「指導」の成立の難しさ
*ひらがなが先か、カタカナが先か
2入学すると読む生活が盛んになる
*書きにくく、読みにくいひらがな
*子供が覚えやすい字
3漢字の多い文は子供には難しい
*読めなくてはつかめない文意
4「死んでいる言葉」は読めない
*経験が左右する読み取る力
*不足している読みの訓練
5漢字の読みは言葉の読みである
*身近に感じる漢字は読める
*読めない漢字の傾向
*体験が語彙の豊かさを生む
6反復練習や応用練習は指導計画の中に組み込む
*定着しないその場限りの指導
*使うことで適切な使用方法を理解させる
《資料》【小学生が読めない漢字】
第三章 読める漢字とその考察
1【ほとんどの一年生が読める漢字】
《分析》ほとんどの字が読めるが「よそ行きの言葉」は正答率が低い
2【ほとんどの二年生が読める漢字】
《分析》「身についていない言葉」は、読めないし書けない
3【ほとんどの三年生が読める漢字】
《分析》「生活に密着した言葉」は、和語・漢語の違いがない
4【ほとんどの四年生が読める漢字】
《分析》「訓読み言葉の指導」は意識して反復練習を
5【ほとんどの五年生が読める漢字】
《分析》語彙を増やすためにも「読書量」を増やすこと
6【ほとんどの六年生が読める漢字】
《分析》「読める漢字」はすべて平凡な日常語
第四章 書けない漢字とその考察
1一年生の書ける漢字と書けない漢字
*【一年生の書ける漢字】
*【一年生の書けない漢字】
《分析》「提示する漢字を増やせ」、読ませるべし
2 二年生の書ける漢字と書けない漢字
*【二年生の書ける漢字】
*【二年生の書けない漢字】
《分析》「読み方を知れば書きたくなる」、その意欲を子供任せにしない
3 三年生の書ける漢字と書けない漢字
*【三年生の書ける漢字】
*【三年生の書けない漢字】
《分析》読みの学習に伴う「書きの指導も重視」を
4 四年生の書ける漢字と書けない漢字
*【四年生の書ける漢字】
*【四年生の書けない漢字】
《分析》「辞書を活用させよ」、辞書は教材であり教具である
5 五年生の書ける漢字と書けない漢字
*【五年生の書ける漢字】
*【五年生の書けない漢字】
《分析》同訓異字や同音異字の「書き分け・使い分け」を
6 六年生の書ける漢字と書けない漢字
*【六年生の書ける漢字】
*【六年生の書けない漢字】
《分析》熟語一字一字の「意味を的確に知らしめる」
7 書けない漢字のまとめと考察
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ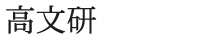

 関連書籍
関連書籍