- NEWS
アジア新風土記(11)東京五輪の夏

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
2021年8月8日、東京五輪が終わった。新型コロナ変異株の蔓延が顕著になっていた7月23日の開会式当日、東京の感染者は延べ19万6400人だった。2週間後の閉会式の日には24万9285人までになり、感染は全国に拡大した。8月9日付けの朝日新聞は、米ジョンズ・ホプキンズ大の集計から世界の感染者は2億人を超えたと伝えた。
世界中で終息の気配が見えないなか、東京に集まったアスリートらはそれぞれの国に帰っていった。医療体制が十分とはいえないインド亜大陸、東南アジア、そしてアフリカなどの国々でコロナがさらに拡散していくのではと心配する。
オリンピックは日本の社会に何をもたらしたのだろうか。
コロナ禍での開催是非に加えてオリンピックが絶対的なものかどうかが論議され、少なくとも社会におけるスポーツの必要・必然性を問い質す機会にはなったのではないか。コロナがなければ、社会は恐らく、オリンピック、スポーツの持つ意味を改めて考えることはなかっただろう。
アジアにはオリンピックに次ぐスポーツ大会としてアジア大会がある。世界新のアナウンスを聞くチャンスなどは稀な大会だ。オリンピックのモットーとして知られる「より速く、より高く、より強く」とは無縁だと感じる競技もある。
大会種目にカバディという競技がある。
インドで人気があり古代インドの叙事詩マハーバーラタに起源を持つともいわれる。各チーム7人が長方形のコートを二分して戦う。攻撃側が「カバディ」と発声しながら相手側に入り、1人でもタッチして自陣に戻れば得点になる。瞬間的な動作に機敏さが求められるとはいえ、子供の遊びといってもいいような競技に、それも一つのスポーツとして容認するゆとりがこの大会にはある。肉体的な「最高レベル」がすべてではないということかもしれない。
この競技を見ていると、走ったタイムを競ったり、1センチでも高くバーを跳び越えたりすることに費やされるエネルギーへの感動とは異質の「極限」への欲求の希薄さに気づく。ゆったりとした時の流れと空間に生きる人たちが共有する息遣い、リズムを感じる。
オリンピックから1週間が過ぎ、8月15日は終戦記念日だ。
政府主催の全国戦没者追悼式は日本武道館で参加者を制限して行われた。
菅義偉首相は式辞で「戦争の惨禍を、二度と繰り返さない、この信念をこれからも貫いてまいります」と述べた。アジアの人たちへの言葉はなかった。
「終戦」という言葉は勝者と敗者を曖昧なものにする。無謀な戦争に負けて国土が占領されたという事実を弱めるだけでなく、戦火に巻き込んだ土地と人への加害者としての責任の回避にもつながっていく。
日本は1945年8月14日のポツダム宣言受諾で第2次大戦を終結させ、社会は翌15日の昭和天皇の「玉音放送」によって戦争が終わったことを知る。
この日はソ連軍がまだ旧満州、樺太、千島列島で日本軍と戦火を交えており、中国大陸では中国共産党と中国国民党の対立が一触即発の状態だった。
米国などの連合国にとっての戦争終結は9月2日の米戦艦ミズリー号での降伏調印式だった。
多くのアジアの国は大戦後に独立したが、「終戦」によって直ちに独立を果たしたわけではなく、韓国が自主独立を取り戻した「光復節」として祝い、北朝鮮が「解放記念日」としている程度だ。
8月15日を「終戦記念日」とする感覚は日本特有のものだと痛感するときがある。アジアの街を歩いても自分一人だけの経験でしかなかった。人々に「戦争が終わった日」という意識はなかった。
メディアは首相式辞に対する相応の記事、論評を報じるが、それもまた一種の儀式と化してしまったのではと思えてくる。その落差は彼らにとってこの日が特段に意味を持つ日ではないと同時に、第2次大戦後も新たな戦争、内乱、動乱が起き、終わり、あるいはいまも続いていることによって生じるものではないか。
大戦はすでに現代史ではなく、近代史に組み込まれようとしている。
朝鮮半島は朝鮮戦争によって南北に分断されたままであり、ベトナムで戦争といえばベトナム戦争、中越戦争になる。
インドネシアはオランダとの独立戦争後、スカルノ、スハルト独裁体制下での長い民主化への闘いがあった。
英領植民地時代に日本軍に3年8か月占領された香港もまた、中国への回帰、香港特別行政区へと目まぐるしく変化していった。
日本だけが今日まで平和な時代を送れたと言ってもよかった。
台湾の大戦の終わりはいつなのだろうか。
日本の植民地台湾として東京と同じ日に「玉音放送」は流れたが、日常生活に変わりはなかった。台湾の人たちが戦争の終結を実感したのは、台湾総督府が連合国の一員としての中華民国(国民政府)に正式に降伏した45年10月25日からではないか。韓国と同様に「光復節」とされたが、社会の関心は薄れていき、2020年の75周年は野党・国民党による音楽会などの記念活動が目立つぐらいだった。
8月の台湾は「鬼月」の別名を持つ旧暦の7月だ。先祖らの霊が帰ってくる中元祭がおよそ1か月続く。「鬼」は日本語で言えば「霊」であり、鬼籍の「鬼」に通じる。
台湾北部の港町基隆の鬼月は、冥界との境である鬼門を開けて鬼たちを迎え入れる老大公廟、商店街の店先、運河の上などに提灯が飾られ、華やかだった。
無数の提灯に見守られ、家々の玄関前などには供物が並び、線香が立てられる。邂逅は長くゆったりと過ぎていく。辻々の小さな廟には絶えず抹香の煙が立ち込め、日々の暮らしに祈りが溶け込んでいた。
基隆の街を彩る提灯を見上げながら、日本の社会では彼岸と此岸の往来に心砕くことが随分と疎遠になったなと思った。旧盆(盂蘭盆)のときに戦争が終わったことへのなにかしらの因縁を感じても、旧盆と戦没者を追悼する日はなかなか結びつかない。死者との巡り合いは同じはずなのに、なぜか追悼の日だけが独立して存在しているかのようだ。
60年以上も前になる。
新潟県三条の母の実家で夜、田んぼの端の山にある墓まで大人たちに連れて行かれたことがあった。九十九折りに木々の葉と提灯の列だけが揺れていた。怖れとわずかばかりの好奇心が異界への歩みを加速させていった。
闇夜か月がかかっていたかは覚えていない。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ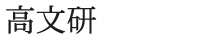
 関連書籍
関連書籍











