- NEWS
梅田正己のコラム【パンセ22】再び、ウクライナ戦争の本質について
寺島実郎氏が雑誌『世界』に長期連載している
「脳力のレッスン」の本年6月号のタイトルは
「プーチンの誤算としてのハードパワーへの過信」
と題されていた。中にこんな一節があった。
(執筆時期は「侵攻開始から五〇日」とあるから、4月中旬ころだろう。)
「プーチンの強引な軍事侵攻が、NATOの結束を促し、
『経済制裁』というソフトパワーを結束させることになった。
/『経済制裁など効かない』とする見解もあるが、グローバル経済の
相互依存構造に参入してしまったロシア経済にとって、
このシステムから排除されることの影響は深刻である。
(中略)
今年のロシアGDPが世界経済に占める比重が
1.0%以下に落ち込むことは間違いない。
世界経済からロシアが消滅すると言っても誇張ではない。」
(下線は引用者)
私自身も当初は似たような予想を持っていた。
しかし予想はものの見事にはずれ、ウクライナ戦争は
出口も見えぬまま長期化し、世界は独裁者プーチンによって
新たな冷戦体制の中に引きずり込まれてしまった。
この予想もしなかった現実を前に、敬愛する友人Sさんもこう嘆いていた。
「冷戦が終わって30余年、いまなお『戦争の世紀』への道をたどっていることに、
私は『絶望』に近い思いを持っています。」
私もまったく同感である。
しかし、それだけになお、世界をいっきょに濃霧のたちこめる
混沌の中に突き落とした「プーチンの戦争」の本質は何だったのか、
できる限り明らかにしておく必要があると思う。
◆東欧諸国のNATO・EU加盟をめぐって
先に私は、水島朝穂・早大教授のオンライン講演の一部を紹介した。
水島教授は、今回のロシアの侵攻が、
「コロナ禍で落ち込んだ米軍需産業の息を吹き返らせる機会にする」
ための「仕組まれた戦争」だと述べていたのだった。
たしかに米国の軍需企業は、ロッキード・マーチンをはじめ
世界の兵器生産企業のベストファイブを独占している
(『週刊エコノミスト』5・17号)。
世界各地の紛争や軍事的緊張の上に、こうした米国の巨大な軍需産業と
同国政治勢力による軍産複合体の思惑が黒い影を落としていることは、
私もまちがいないと思う。
しかし今回の戦争をいわば「状況証拠」だけを見て、
米国の「謀略」と決めつけてしまうのは、短絡的すぎるのではないか。
水島氏はまた、
「ウクライナが東部での戦闘を続ける中で、米国はNATOの東方拡大を進めた。
これらがロシアを刺激し、軍事行動を誘い込んでいった」
(JCJ機関紙の要録による)と分析している。
NATOの東方拡大によるロシアへの圧迫は、プーチン自身も主張している。
ソ連邦が解体し、ワルシャワ条約機構が解消された後、米国をはじめ西側諸国は
NATOの東方への不拡大を約束したにもかかわらず、それを破ってかつてソ連
圏の圏内にあった東欧諸国を次々に傘下に取り込んできた。
この上、ウクライナまで取り込まれれば、ロシアは丸はだかにされてしまうではないか、
そんなことは絶対に許すわけにはいかない、という危機感がプーチンを
ウクライナ侵攻へ駆り立てたというわけである。
つまり今回の「特別軍事作戦」は、それを防ぎとめるための「防衛戦争」だった
ということになる。
しかし、事実経過を見れば、その説明が後付けだったことがすぐにわかる。
プーチンが大統領となり、ロシアの政権をとったのは2000年である。
それ以前の10年間、1990年代のエリツィンの時代は、
ロシアはハイパーインフレをともなう未曽有ともいえる混乱期がつづいた。
そうした中、1999年に、ハンガリー、チェコ、ポーランドがNATOに加盟、
5年後の2004年にバルト三国、スロバキア、ブルガリア、ルーマニアなどが
つづいてNATOに加盟した。
一方、EU加盟の方はどうだったか。
やはり2004年にハンガリー、チェコ、ポーランド、バルト三国、
スロバキアが加盟、2007年にブルガリア、ルーマニアなどが加盟している。
つまり、プーチンの独裁的な権力が確立する以前に、
東欧諸国はこぞってNATOとEUに参加しているのである。
では、なぜソ連邦解体後、東欧諸国はこぞってNATOやEUへの加入を急いだのか。
理由は、ソ連型の一党独裁による計画経済や経済統制、その結果としての
生産性の低落による経済的貧窮、秘密警察を使っての恐怖政治から、
一刻も早く逃れたかったからである。
つまり「タタールの軛(くびき)」ならぬ「ソ連(ロシア)の軛」から脱却して、
西欧型の自由主義(資本主義)世界へと仲間入りしたかったからである。
東欧諸国のNATO、EU参加は、米国などの積極的勧誘によるのではなく、
いわば歴史的必然としてのなりゆきだったと私は考える。
なお、ロシアがG7(サミット)に加わるのはエリツィン時代の1998年、
そこからプーチンが離脱するのは2014年、クリミア半島の一方的併合によってである。
またこの間2005年には、プーチンとドイツのシュレーダー首相が、
天然ガスの海底パイプライン「ノルドストリーム」建設に合意、
その調印式で握手を交わしている。
つまり、2000年代にはまだプーチンと西側諸国とは敵対関係にはなかったのである。
では、いつごろからその関係が崩れだしたのか。
◆「世界の警察官」退場の後に
さる8月2日夜、NHKの番組「混迷の世紀」シリーズが始まった。
NHKに対してはいろいろと批判がある。
しかし、NHKスペシャルほかそのドキュメンタリー番組はすばらしい。
今回の「混迷の世紀」プロローグから、私も実にたくさんの事実(証言)を教えてもらった。
以下、この番組から多くの証言を引用させていただく。
冒頭、2005年から5年間、NATOの事務総長をつとめたラムスセンが証言する。
2010年、プーチンとにこやかに笑いながら、
互いに「戦略的パートナー」となることを約束して握手する映像のあと、
元事務総長は語る。
「当時、私たちはプーチン大統領が抱いていた野心を過小評価していました。
彼には、旧ソビエトの領土でロシアの偉大さを取り戻そうという野心があったのです。
後から考えてみれば、彼がクリミアを併合したとき、
私たちの対応があまりにも手ぬるかったのです。
制裁は軽すぎました。
われわれが差し伸べようとした手を、ロシアは振り払ったのです。」
さらにそのあと、オバマ政権(2009~2017年)時代に国防長官を務めた
パネッタがこう証言する。
「米国が世界の警察官でなくなったことが世界の秩序を不安定にした。
続くトランプ大統領のときには自国第一主義を主張し、世界の同盟国を
これまでのようには支援しない姿勢を明らかにしました。
またバイデン大統領についても、プーチン大統領は、ウクライナへの侵攻を
検討するに当たって、米国はアフガニスタン問題への対応で疲弊していると
見てとったのです。」
じっさい、米国はだいぶ前から「世界の警察官」の役割を担えなくなっていた。
その最大の原因は、2001年の9・11のあと、ブッシュ(子)大統領が反射的に
反応して「対テロ戦争」を呼号し、アフガン空爆に突入したことである。
以後、ブッシュはイラクが核兵器と大量破壊兵器を隠匿していると決めつけ、
英国と組んでイラクに侵攻、5千年の歴史をもつ都バグダッドの壊滅を含め
イラクを叩きつぶした。以後、中東はたえざる騒乱の中に巻き込まれる。
こうして米国がつくり出した安全保障秩序の撹乱の空隙をついて、
プーチンはウクライナへの侵攻を決行したのである。
◆エネルギー資源を「戦略物資」として
2000年にプーチンが大統領に就任したとき首相となり、
2004年まで務めたミハイル・カシヤノフは、こう証言した。
「大統領になった当初、プーチンは民主主義者を装っていました。
しかし2004年頃からその正体を現しはじめます。
2003年にジョージアで民主化運動が起こり、次いで2004年、
ウクライナでオレンジ革命が起こった頃からです。
彼にとって人権は何の意味もありません。
彼はゆがんだ世界観をもったKGBの将校のままだったのです。」
「プーチンが最も恐れていたのは、もしウクライナが民主主義国家として繁栄した場合、
ロシア国民が『なぜ自分たちはそうなれないのか』と疑問に思いはじめることでした。
ロシアはいまや完全な権威主義国家となり、全体主義へと向かっています。
『プーチンのロシア』という全体主義です。」
プーチンはいま、天然ガスや石油を自国の「戦略物資」として振りかざし、
覇権国家に近づこうとしている。
この戦略構想を、プーチンはだいぶ前から温めていたようだ。
1999年に彼は、「ロシア経済の開発戦略における鉱物資源」
という論文を書き、その中でこう述べているという。
「膨大な天然資源をもつロシアは、先進国の中でも特別な存在である。」
またドイツとの「ノルドストリーム」建設調印の翌2006年には、
こうも語っている。
「エネルギーは経済構造を変えるチャンスだ。
これによってロシアは世界市場でしかるべき地位を獲得する。」
こうしてプーチンは、「ロシア帝国」を再現するという野心を果たす道を
着々と踏み固めてきた。その道の最先端にあるのが、今日のウクライナ侵攻なのである。
*
それにしても、このプーチンという人物をどうとらえたらいいのだろうか。
今回のウクライナ戦争の原因については、国際政治の「状況」からの見方がある。
米国の軍産複合体による謀略説やNATOの東方拡大によるロシア圧迫説、
またウクライナ内部の「ネオナチ」による策謀説などもある。
しかし私は、やはりプーチンというきわめて特異なパーソナリティーを
中心にすえて、今回の事態を見るべきではないかと思う。
歴史上、特異なパーソナリティーが世界を動かした例はいくつもある。
近代ではヒトラーやムッソリーニがすぐに浮かぶ。
こんにち現存するのは、「中華帝国」の習近平やUSAのトランプである。
プーチンもその列に加わる。
現代の政治学は、状況論だけでなく、こうした特異なパーソナリティーを、
重要な政治的ファクターとして客観的に把握すべきではなかろうか、と
いうのがこの小論を書いての感想である。 (了)
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ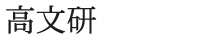
 関連書籍
関連書籍

















