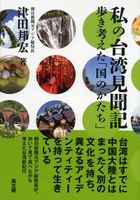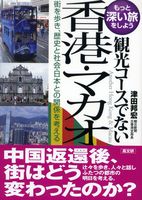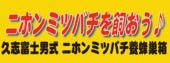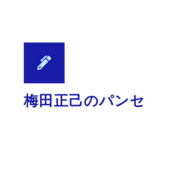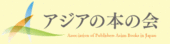- NEWS
アジア新風土記(97) シンガポールの幸運

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
シンガポール・チャンギ空港の記憶は限りなく広がる淡く柔らかな空だった。
晴れた日、機体が高度を落としていくとき、窓からの眺めにいつも弾むような開放感があった。
なぜだろうか。
滑走路はシンガポール島東端の海に面しており、着陸直前まで海上や自然豊かなマレー半島上空を飛行するからだろうか。
少しばかり満ち足りた心は空港からのイーストコーストパークウェイのレインツリーで一層膨らんでいく。
ネムノキにも似た木々は樹冠が半球型に枝を伸ばして道を大きく覆い、たわやかな葉が明るい陽光を受け止める。
太陽と緑の恵みを感じさせるパークウェイは「ガーデンシティ」と呼ばれるシンガポールへの最適な「道案内人」だった。
高速道はマリーナエリアを見下ろしながら街の中心部へと入っていく。
大通りだけでなく、公園、団地の広場などに多種多様な草木との出会いは、高温多湿な熱帯の気候に合う植物を世界各地から収集して造り出された。
高速道、歩道橋の下などの日当たりの悪い場所でも苦にしないつる性植物を探し出すなど、生育植物の半数以上が外来種といわれるまでになった。
レインツリーも中央アメリカ原産の常緑高木で、雨が近くなったり日の光が弱くなったりすると葉を畳むことで知られる。
シンガポールには1876年に米国から持ち込まれたという。
在来種の筆頭格は東南アジアから南太平洋地域にかけて分布するアンサナ(インドシタン)か。
市街地の南北に3キロほど続くオーチャードロードは長く垂れたアンサナの大木が涼しげな木陰をつくる。
樹高は30~40メートルになり、バラのような香りからローズウッドという英名もある。生長は早く、1960年代から積極的に植えられていった。
一帯はかつて果樹園(オーチャード)とコロニアル様式で建てられた高級住宅街だった。ショッピングセンター構想が持ち上がり、次第に高級ブティック、カフェ、デパートが連なる目抜き通りが誕生する。
日本式スーパーをアジアに持ち込んだ「ヤオハン」も74年にオープンする。
機能的なスーパーは市場の概念を一変させて、人気を誇った。
アジアの人たちがそのノウハウを習得するのにそれほどの時間はかからず、ヤオハンはやがて消えていく。アンサナの下を歩きながらそんなことを思い出す人は昔のシンガポールを知っている人だけだろう。
緑豊かな樹木に囲まれ、洒落た通りがあり、多くの市民が暮らす団地には生鮮食料品で溢れたスーパーがあり、ごみの散乱などは滅多にない清潔な街は、人々の生活に程よい環境が整っていた。
一方で、半年ほどを過ごして街に慣れてくると何か物足りなさを覚えたのも確かだった。人と人のふれあいはそつがなく淡泊で、ぎらぎらとした目はあまり見かけなかった。
明るく爽やかな社会は人間の性というか剝き出しの本性というものを晒す場には相応しくないのかもしれない。風景もまた行儀のいい佇まいを見せ、郊外の自然保護区などに行かなければ野放図な自然はほとんどなかった。
宗教色の希薄な街とも言えた。リトルインディア、チャイナタウン、あるいはアラブストリートを歩けば、ヒンズー寺院、中国式の廟、モスクは当たり前のようにあった。
繁華街を外れても寺院、廟などを目にすることはあり、敬虔な祈りを捧げる人は珍しいことではなかった。
ただ、シンガポール全体から発散される空気はあくまで透明であり、強烈な信仰心の発露をみるような場に遭遇する機会は稀だった。
宗教寺院も統制のとれた都市国家の欠かせないパーツとして配置されているのではという思いさえした。
宗教を異にする人たちの対立が起こりにくい雰囲気は宗教紛争などが生じる余地を少なくする。
「安全な街」は国際的な会談、会議の場を提供する。
2015年の中国・習近平党総書記と台湾・馬英九総統との初の中台首脳会談、3年後のトランプ米大統領と金正恩・北朝鮮総書記の首脳会談は、妨害工作などを極力排除できるということだったのだろう。
オーチャードロードの南にほぼ平行するシンガポール川は小さな川だった。
往時も同じような水量だったのだろうか。
コンクリートで固められた両岸が川幅を見かけ以上に狭くして運河のようだ。
河口のマリーナベイ近くの左岸には英国の植民地行政官だったラッフルズの像が立っている。
ラッフルズは1819年に上陸、東インド会社交易所を開いてシンガポールの礎を築く。
インドと中国を結ぶマラッカ海峡の要衝の地は、後背地のマレー半島から産出される錫と栽培されたゴムの集積地として発展していった。
日本の敗戦後は英国直轄領ながら自治権を確立、マレーシア連邦加入から2年後の1965年に分離独立する。
リー・クアンユー首相は国家の生存をかけて、外国企業の誘致、人材養成のための英語を中心としたエリート教育などを打ち出す。
緑化政策によって快適、清潔な国というイメージづくりにも成功した。
2025年、シンガポールは建国60年を迎えた。
政治的な安定は人民行動党(PAP)の一党独裁体制を維持することで保たれてきた。
20年の総選挙(一院制、定数93)はしかし、83議席を獲得したものの投票率は前回を下回る61.2%に落ちた。
次の総選挙は25年11月までに実施される。長期政権の是非が改めて問われることになる。
国土は最大のシンガポール島と62の島々でなり、720平方キロ。
東京23区ほどの小国に600万人が住み、人口密度の高さはマカオ、モナコに次ぐ。香港に比べると面積は65%と狭く、人口は150万人少ない。
英領植民地の歴史を持つシンガポールと香港がその時代を終えたとき、「自立」への歩みは異なったものになった。
シンガポールは水の25%をマレーシアに依存、食料も9割以上を輸入に頼り、自国生産の進む鶏卵でさえ3割ほどだ。
それでも、水資源の自力開発、食料品の輸入先の分散化などに活路を見出してきた。香港は中国に返還されたとき、水、生鮮食品の大半は大陸から得ていた。
供給をストップされれば立ち行かなかったが、中国がなければ自力で生き残る道を探せたのではないかと考えることがあった。
二つの都市の一方は独立を果たし、一方は独立の機会さえなかった。
大国が「隣人」として存在しなかったシンガポールの幸運を思った。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ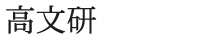
 関連書籍
関連書籍