- NEWS
梅田正己のコラム【パンセ17】 明治維新論をめぐる熱い論議を
◆『明治維新の歴史』を執筆して
梅田 正己
次の一文は、先月発行の北岡伸一著『明治維新の意味』(新潮選書)序章の一節である。
「多くの途上国にとって、非西洋国から先進国となり、伝統と近代を両立させている日本という国は、まぶしいようなすごい国なのである。いつか日本のようになりたいと思っている国は数多いのである。」
このように書く、元国連大使、現在はJICA(国際協力機構)理事長の東大名誉教授(日本政治史)の明治維新観がいかなるものであるかは説明するまでもないだろう。
一方、正反対の見方もある。
司馬遼太郎は『この国のかたち』第一集(文春文庫)で、明治維新は「革命思想としては貧弱というほかない」尊王攘夷は「外圧に対するいわば悲鳴のようなもので」「革命の実践という面では、ナショナリズムという、可燃性の高い土俗感情に火をつけてまわることだった。」と一蹴している。
これが「志士」たちを主人公に何篇もの作品を書いてきた司馬の維新観なのである。
ここに一端をみたように、明治維新については白と黒の真逆の評価が同居する。この国の近代史の始点であり、その後の方向を決定した出来事について、すでに150年を経た今も、国民的認識は定まっていないのである。大きな謎というほかない。
維新という歴史的出来事について、科学的な実証と論証にもとづき基本的な認識の大枠を示す第一の責任は、もちろん歴史学にある。
ところが、明治維新研究の現状について私が最もラディカルな問題提起者とみる奈良勝司氏は『明治維新をとらえ直す』(有志舎)で、「2018年現在、明治維新研究は明治維新論の再構築とその体系的な提示という意味ではある種危機的な状況にある」と述べ、「さながら我々は、肝心の目的地や航路を知らないまま、船内パーティの熱気に酔いしれるタイタニック号の乗客のようだ」とまで極言している。
つまり研究の現状が、対象を狭い範囲に限定してそれを深く掘り下げる、いわばタコツボ的状態に陥っていて、研究者自身が維新の全体像を見失っているのではないか、という指摘なのである。
そのいわば維新認識の空白地帯に、先に見たような浅薄で無責任な維新論が野放しで横行しているのではないか、というのが私の見方である。そこでこの秋、本業は書籍編集者であるが、維新の全体像とその歴史的位置づけにチャレンジしてみた。『明治維新の歴史――「脱封建革命」としての幕末・維新』(高文研)の一冊である。
自分でオリジナルな試みと思っている点がいくつかある。
たとえば、明治維新を「脱封建革命」と規定したことである。江戸時代、列島は三百近い「くに」に分割され、圧倒的多数の人民は身分制・門閥制で守られた上級武家の支配下で政治的無権利状態に置かれていた。それが封建制だった。維新により列島は中央集権の統一国家となり、人民は身分制から解放され、政治参加の道を遠望できることとなった。封建制支配からの脱却、それが維新の本質だったのである。
コロンブスの卵のようであるが、シンプルに考えればそう言えるのではないか。
もう一つ挙げれば、維新への道を「尊王攘夷」思想の形成過程から叙述したことである。司馬はこれを「外圧に対する悲鳴」にすぎないと冷笑していたが、これこそが志士たちを変革へと駆り立て、さらに尊王思想は近代日本形成の国家原理となり、150年後のいまも憲法の第一章を占めているのである。
尊王思想に対する軽視は、自らの近視眼的史観を露呈しているにすぎない。
後半は自家広告になったが、明治維新をどう見るかは、歴史認識の根幹にかかわる。小著はわかりやすく一気に読めるのが自慢である。これが誘い水となって、市民のみなさんの間に、できれば専門研究者も加わって広く論議が巻き起こったら、と夢見ている。
(※本稿は新聞『思想運動』2020・11・1号に寄稿したものです。)
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ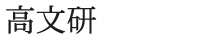
 関連書籍
関連書籍

















