- NEWS
アジア新風土記(51)バーミヤン

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
.jpg)
バーミヤン渓谷
ポプラの木々(百合本茂氏撮影)
.jpg)
大摩崖
日差しが日々柔らかくなって草木が芽吹くころ、アフガニスタン・バーミヤンのまだ見たことのない春を思い描くことがある。
岩山と赤い鉄錆色の土があたりを支配する風景の中に、南に連なる雪山からの雪解けの流れに添うポプラ並木は萌芽のときを迎えているのだろうか。
そして、かつて北の大磨崖にあった二体の大仏はどのような眼差しで季節の移ろいを眺めていたのかと追想してみる。その大仏はいまはない。
岩肌に主の失った眼窩のような巨大な仏龕(ぶつがん)があるだけだ。
バーミヤンは首都カブールから北西230キロのところにある。北のヒンズクシー山脈と南のコーイババ山脈に挟まれた標高約2500メートルの渓谷が東西に800キロほど続いている。
高さ100メートルもある大磨崖には1世紀ごろから北方のバクトリアによって石窟寺院が築き始められ、最盛期には石窟が千を超え、数千人の僧侶が祈りの日々を送ったという。
二つの大仏は6世紀から7世紀にかけて建立され、西大仏は高さ55メートルの弥勒、東大仏は38メートルの釈迦とされる。資料、碑文の類は見つかっていない。.jpg)
西大仏
中国の唐の時代、僧玄奘(げんじょう・三蔵法師)はインドに仏教の修業と経典を求めて629(太宗・貞観3)年、長安を旅立ち、翌630年の晩秋には天山山脈から現在のウズベキスタンを経てバーミヤンに入った。
彼は開眼供養してからまだそれほどの年月が経っていない巨大な摩崖仏を目の当たりにしたことになる。
玄奘が645年に帰朝するまでの見聞記を編纂した『大唐西域記』をみる。
「梵衍那国(バーミヤン)は東西二千余里、南北三百余里で、雪山の中にある。人は山や谷を利用し、その地勢のままに住居している。国の大都城は崖に拠り谷に跨がっている。(中略)宿麦(むぎ)はあるが、花・果は少ない。牧畜によく羊・馬が多い。(中略)伽藍は数十カ所、僧徒は数千人で、小乗の説出世部を学習している」(『大唐西域記1』(東洋文庫653、水谷真成訳注、平凡社、1999年)
『大唐西域記』は二つの大仏についても触れている。
「王城の東北の山の阿(くま)に立仏の石像の高さ百四、五十尺のものがある。金色にかがやき、宝飾がきらきらしている。東に伽藍がある。この国の先の王が建てたものである。伽藍の東に鍮石(とうせき)の釈迦仏の立像の高さ百尺余のものがある」
「立仏の石像」はイスラム教徒によって顔の部分が削り落とされ、2001年3月にはタリバン政権によってすべてが爆破された。
イスラム教スンニ派パシュトゥン人主体のタリバンは1996年にカブールを制圧する。バーミヤンに暮らす少数派シーア派ハザラ人は抵抗したものの2年後に陥落、大仏の爆破作業にも駆り出された。
作業に携わった人が振り返る。
「岩穴に掘られた大仏たちは、隣人のように身近な存在だったのです」
「西大仏の頭の部分からロープを垂らし、ロープにぶら下がって西大仏の体のあちこちに爆薬を埋める穴を掘りました。全ての穴を掘るのに25日間かかりました。一つの穴に7キロずつ爆薬を詰めました」
(朝日新聞DIGITAL、2021年11月4日)
大仏破壊はイスラムの偶像崇拝禁止の教えを厳格に守ったからか。
顔のない大仏には、異教徒が忌避するだけの明確な理由はなくなったのではとも思う。
パシュトゥン人にとっては異教の仏像と共に生きてきたハザラ人が許せず、そのことが破壊に繋がったのか。
タリバン政権は2001年秋の米国の同時多発テロ後、米軍を中心とする多国籍軍の軍事介入によって瓦解する。
石窟内壁画保存などの遺跡修復は大磨崖に地雷が埋められたままの状態下で動き出したが、21年8月のタリバン復権は活動を頓挫させた。
アフガンがまだ王国だった1969年10月、カブールを午前3時過ぎ発のバスで半日かけてバーミヤンの谷に入った。季節は秋の盛りだった。
バスが谷の入口から奥へと進んでいくうちに大磨崖が次第に大きくなっていき、摩崖仏もその巨大な姿を見せてきた。
ターバンを巻いた男たちがロバに跨って通り過ぎていく。
頭に籠を載せた女たちが砂礫だけのような丘を歩いていた。
遠くの雪山と前衛の土色の山々がくっきりとした輪郭をもって分れ、水の豊かな川筋にはすでに黄色く色づいたポプラの木々があった。
いくつもの畑は少し盛り上がった畔によって仕切られ、麦などの作物を見かけず、羊の群れがいた。
大仏の目の前に並行する通りにはポプラ材を渡した平屋建ての建物が軒を連ね、金物などの日常雑貨を売る商店、食堂などがあった。
人々の貧しさは容易に見て取れたが、暗さ、貧困への絶望といったものを感じることは稀だった。
西大仏の頭部までは回廊のようなルートがあった。
崖の中を洞穴を歩く感覚で上っていくと、頭部の真後ろに辿り着き、丸い額縁の中の絵の様に谷を見下ろすことができた。
壁にはわずかに壁画が残っていた。
大摩崖中程から谷を見下ろす
西大仏頭上脇からの眺め(百合本茂氏撮影)
壁画の仏の顔、手、指先の描き方には中央アジア、中国の壁画などで「鉄線描」として知られる技法が使われていた。
一定の速度、同じ太さによる筆の運びは、強く引き締まって凛とした筆致をみせる。
中国・亀茲(きじ)研究院の趙莉研究員によれば、唐代初期の僧で中央アジア・ホータン王国出身の尉遅乙僧(うっちいっそう)が生み出したという(NHK特集『シルクロード 壁画の道をゆく』)。
技法はホータンから南のバーミヤンまで伝わったということだろうか。
鉄線描は敦煌(とんこう)の壁画などを経て日本にも伝播され、法隆寺金堂六号壁画の阿弥陀如来像に色濃く投影された。
西大仏頭上の壁画
法隆寺の仏像群は、東京・上野の東京国立博物館の法隆寺宝物館で見ることができる。
菩薩半跏像、観音菩薩立像などはいずれも7世紀の飛鳥時代の金銅仏だ。
明治初期の1868(慶応4)年の神仏分離令直後から広まった廃仏毀釈運動が法隆寺に累が及ぶことを恐れて皇室に献納、後に博物館に収蔵された。
仏像の破壊は古都だけでなく全国の寺社で続いた。
バーミヤンの大仏爆破から22年が過ぎたいま、悲しく愚かな爆破だったと糾弾する気持ちに変わりはない。
一方で明治のことを考えれば、イスラム教徒の蛮行と言い切れるかという思いも心のどこかにあった。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ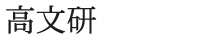
 関連書籍
関連書籍












