- NEWS
アジア新風土記(89)マラッカ

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
日本のタンカーに乗せてもらってペルシャ湾からインド洋を横断、
マラッカ海峡を通過したことが学生時代にある。
海峡は狭く、航路も限られている。
大型のタンカーがすれ違う時にはぶつかるのではないかという不安が掠めた。
タンカーのだだっ広い甲板左舷からマレー半島を望み、どこかにマラッカの街が
あるはずだと眺めていた。
大航海時代の海峡もまた、タンカーに比べサイズこそ圧倒的に小さいものの、
帆船、カラック船(ヨーロッパの代表的な帆船)が縦横に行き交っていたことだろう。
タンカーはゆっくりと進んでいた。
その船足は遥か昔のことに思いを馳せるのに程よい速度だった。
「マラッカ」という言葉は不思議な響きを持っている。
マラッカ王国の都、ポルトガルのアジア進出の橋頭保になった港町の名前は、
歴史上の王国、港町といった枠を超えて、アジアを旅する人、あるいは旅を
思い描く人を、なにか夢見心地の世界へと誘(いざな)う魔法の呪文のように
聞こえてくる。
この街をこの通りを、どれだけの人が野望、野心を胸に秘めて
彷徨(さまよ)っていたことだろうか。
商人は少しでも利を求めて店先に溢れ、宣教師は未知の大地の伝道に
心躍らせる。そして新天地を求めて故国を後にした無数の男たち、女たちがいた。
マラッカ王国の建国は1400年ごろとされる。
インドネシア・スマトラ島の王子がマレー半島を北上、マラッカの地に王朝を打ち立てた。
インド洋と南シナ海を繋ぐマラッカ海峡の中程に位置する立地は、中継貿易の要衝だった。
インド・ベンガルからは織物が、中国からは絹糸が、
そして香料(モルッカ)諸島からは様々なスパイスが集まり、
また各地に運ばれていった。
ビルマ(ミャンマー)のルビーも貴重な産物だった。
商人らは季節ごとに風向きを変える季節風を利用した。
マラッカの人たちは夏になると1か月程かけてインド洋を横断、
ベンガルで商いをする。
冬になると今度はマラッカに向かう風とともに帰ってくる。
ベンガルの商人たちもこの風に乗ってマラッカに入り、
次の季節風が吹き始めると港を後にする。
ポルトガルのインド在住商館員だったトメ・ピレスは『東方諸国記』に、
マラッカで取引した人々と地方について、カイロ、アデンのイスラム教徒に
始まり、ペルシャ人、トルコ人、アルメニア人のキリスト教徒、
アラカン(ミャンマー=筆者注)の商人、シナの人々ら63の名を挙げ、
「マラカ(マラッカ=同)でその住民とマラカに居留している人々が断言するところによれば、マラカの港ではしばしば八十四の言語がそれぞれ(話されるのが)見られるということである」
と書く。
(『大航海時代叢書Ⅴ』、生田滋ら訳、岩波書店、1966年※品切れ)
ポルトガルは1498年、ヴァスコ・ダ・ガマのインド・カリカット到達後に
ゴアを占領、1511年にはマラッカを攻略する。
トメ・ピレスが訪れたのは王国滅亡の翌年だった。
ポルトガルの統治も長くは続かず、支配者はオランダ、イギリスと
交代していった。
マラッカの街は小さな街だった。
とても呪文を唱えて辿り着くような雰囲気ではなかった。
クアラルンプールから陸路をバスで来たからか。
それでもタンカーから遠望した時の気持ちを思い起こしながら歩いた。
マラッカ川。積み荷を満載した舟の往来を想像する。(写真はいずれも百合本茂氏撮影)
街の中央をマラッカ川が流れている。川幅は30メートルほどだ。
河口に埠頭らしきものは見当たらなかった。船着き場もなかった。
すでに港としての機能は失われていた。
遠浅の海は交易船が着岸できず、沖合に錨を下したまま小舟だけが川の両岸に並ぶ商家に様々な荷を降ろしていったのか。
川面に迫り出すような建物の一つ一つに、往時の繁栄をみる。
川筋は次第に狭く、蛇行していった。
河口から約1キロのオランダ広場は周囲を赤紫色の建物で囲まれていた。
オランダがポルトガルを駆逐した1641年から市庁舎などを建てたところだ。
当時の白の漆喰づくりは英国が19世紀になって塗り替える。
国家、都市の興亡はかつての「存在」を打ち消す作業と重なる。
オランダ広場にはオランダ東インド会社時代の建物が残る。
マラッカ川左岸の広場から橋を渡ったハン・ジュバッ通りを一つ北に曲がると、
様々な寺院に出会う。
川の近くからヒンズー教のスリ・ポヤタ・ヴィナヤガ・ムーティ寺院、
イスラムのカンポン・クリン・モスクには白いミナレット(尖塔)があった。
さらに進むと中国風のチェン・フン・テン寺院(青雲亭)の廟が飛び込んできた。どの寺にも人々の三々五々祈る風景があった。
その姿を見ながら信心の心はみな一つなのだと感じる。
一方で、心の安寧を求める人たちにもスイッチの切り替わるときがあり、
宗教上の教理をもとに宗教戦争が繰り返されてきた歴史を思う。
三つの寺は17世紀から19世紀にかけて創建された。
マラッカが王国の時代、通りには何があったのだろうか。
チェン・フン・テン寺院は線香の香りに満ちていた。
ハン・ジュバッ通りの中国人街を通り抜けて、
ひっそりとしたトゥン・タン・チェン・ロック通りに出る。
オランダ時代はヒーレン通りと呼ばれ、財を成したオランダ人の邸宅が
両脇に連なっていた。中国人富裕層が後を継ぐ。
屋敷は奥に細長く、海から直接出入りできる船着き場を持つ家もある。
人通りは少なく、商売になるのかというほど飾りっ気のない店構えの奥は
宝飾の店だった。見るからに高そうなものはなかった。
高価な宝石はきっと奥に仕舞い込まれ、顧客の注文に応じて
取り出してくるのかもしれない。
いまでもビルマ産のルビーが密かに買い手を待ち構えているような気がした。
オランダ広場南のセント・ポールの丘を回り込むようなコタ通りの先には
サンチャゴ砦があった。
ポルトガルがオランドとの戦いに備えて築城した砦の痕跡はレンガ造りに
白の漆喰が辛うじて残る門だけだった。
急な坂道を登り、頂上はフランシスコ・ザビエルの遺骨が一時期納められた
セント・ポール教会の遺構だった。
ザビエルはポルトガルの占拠から34年後に初めてこの地に赴く。
中国、香料諸島などの布教に向けての日々をしばらく送ることになる。
セント・ポール教会の遺構。ザビエルはこの丘で日本布教を思い立たせた鹿児島出身のヤジロウと会う。
サンチャゴ門。なせこの門だけが残ったのか。
教会跡から市街地を抜け、浜辺の波打ち際に立つ。
少し赤茶けた海の色は沖に向かって黄土色からエメラルドグリーンへと変わっていった。
タンカーが数隻、航行していた。
小さな船影だった。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ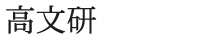
 関連書籍
関連書籍











