- NEWS
アジア新風土記(36) アフガン女性の「ブルカ」

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
アフガニスタンの田舎をバスに揺られていたとき、時折、
道端に立ってバスをやり過ごすアフガンの女性たちを見かけた。
みな「ブルカ」を着ていた。
ブルカは頭からすっぽりと覆り顔の部分だけが網目になっている
伝統的な衣装で「チャドル」とも呼ばれている。
イスラム世界でよくみかける女性用のベール(ヒジャブ)の一種だ。
彼女たちがほんの一瞬バスを見上げた時、
網目の奥から見つめる目があった。
後方に小さくなっていく姿を追いながら、
歩いてどこに行くのだろうかと思った。
辺りに集落らしきものは見当たらなかった。
バスの行く方向にも町はまだ遠かった。
見渡す限りの砂と石が混ざってごつごつとした砂漠の
はるか先の山間に人々の暮らすところがあるのだろうか。
砂が風紋を広げていくような柔らかな砂漠とはおよそ異なる
「砂漠」とそこに暮らす人たちとの出会いは、
異装の人たちによって一層脳裏に焼き付いた。
アフガンの男たちは物静かで落ち着いた眼差しを湛えていた。
バス旅行の途中、エンジントラブルで道路わきに野宿したときも、
当たり前のように薪を集めてきて火を起こし、簡単な夜食を準備する。
いつも非常食を用意しているかのように、だれかがナンを取り出し、
まただれかが卵焼きをつくって、乗客らに分け与えていた。
カイバル峠からアフガンに通じるパキスタンの国境の町ペシャワールでは、
だれもが肩に当たり前のようにライフル銃を掛けていたが怖さはなかった。
峠を越えてトラックの荷台に乗った時もライフルの男たちは穏やかだった。
滋味に満ちた目が顔の深いしわによく似合った。
男たちのことは次から次へと頭に浮かんでくるのだが、
女性たちの記憶はほとんどない。
ブルカ姿からは表情が読み取れなかったことも理由の一つかもしれない。
アフガンの地域医療、農業振興に尽くした中村哲医師は
女性たちについてこんなことを書いている。
「保守的なイスラムの世界で女たちのことを語るのは容易ではない。外国人が町で接するのは普通上流の西欧化した女たちで、山岳地帯を行く登山家はかたくベールに顔をとざして逃げ去る女たちに面食らう。(中略)10年もペシャワールにいて、じつは私もよくわからない。男たちはめったに女の話をしないし、たずねもしない。(中略)確実なのは、彼女らはその社会の中でふさわしい、女としての地位と役割を十分演じているということだ」
(『アフガニスタンの診療所から』ちくま文庫、2005年)
中村さんは「十分演じている地位と役割」について具体的には触れていない。
長い医療現場からの経験がそう言わせたのだろう。
彼は1984年にペシャワールに初めて赴任、医療活動を始める。
当時のアフガンには中村さんが感じたような女性の尊厳が
守られる社会があったということか。
2022年8月、アフガン社会にイスラム法「シャリア」を厳格に適用する
タリバン政権が復権してからまる1年が経った。
1996年から5年間、国土の約8割を実効支配したときの女性軽視の姿勢が
国際社会から強い批判を浴びたことで、2度目の政権奪取当初は女性の権利の
保障を表明していた。
しかし、「男女平等」の約束は実現されていない。
テレビの報道番組でタリバン報道官にインタビューした女性キャスターは
国外に逃れ、街の美容院の看板にあった女性の顔は塗りつぶされた。
女学生の少ない大学は服装などの制限付きで通学許可が出たが、
130万人といわれる女子中高生は2022年3月から通学が認められていない。
5月にはすべての女性の外出時のブルカ着用が義務づけられた。
2019年12月4日、中村さんは車で移動中に何者かの銃撃を受け殺害された。
一緒に殺されたアフガン人の遺児たちの思いを2022年2月13日付けの朝日新聞で知る。
運転手の長女(14)は学校に行けず
「ドクター・ナカムラのような立派な人に」
という父との約束を果たすことができない。
同じく殺された警官の長女(15)は診療所も女性医師もいない村に育った。
「医師になって貢献したいと」と願うが勉学の道は閉ざされたままだ。
中村さんは
「パシュトゥン(アフガンの最大民族=筆者注)の女たちには
それぞれの個性的な顔がある。
(中略)かがやき、あくの強さ、しぶとさと弱さ、
高貴と邪悪がすなおにとなり合っている」とも書いた。
彼の女性観は、タリバン政権下でどのように生き続けるのだろうか。
『明日になれば~アフガニスタン、女たちの決断~』という映画を見る。
女性監督サハラ・カリミさんが中村さん殺害の19年に首都カブールで製作する。
街はタリバンなどによる自爆テロなどが続いていたが、通りは車も人も行き来して、自由な空気が残っていた。
映画は頑迷な祖父と男尊女卑の夫の家で暮らす妊婦、
離婚を決意した矢先に身ごもったことを知るテレビキャスター、
妊娠を告げた恋人が去り従兄との結婚に同意する娘の話を
オムニバス風に描いていく。
妊婦は庭で転んで胎児が動かなくなったと夫に病院への付き添いを頼むが、
友人の接待を優先して取り合わない。
キャスターは文盲の従兄との結婚を断り、大卒者を選んだ。
結婚直後から夫の浮気に悩まされ、夫の両親からは石女(うまづめ)と
蔑まれる日々を送っていた。
父親が自爆テロで死んだ娘は叔母の息子との結婚前に
子供を堕(お)ろさなければならなかった。
娘は友人と違法の診療所に向かう時「身元を隠すため」にブルカを着る。
画面は三人の女性が待合室で期せずして出会うところで終わる。
キャスターと娘が訪れた理由はわかる。妊婦はどうなのか。
お腹は大きなままだった・・・。
「心の自由、それが彼女たちの決断」とパンフレットにはあった。
中絶は「心の自由」を得るための手段であり、人生の選択なのか。
アフガンで新たな命を授かるということはどういう意味を持っているのか。
監督のカリミさんは国外に脱出した。
「伝統的、父権的な社会で、妊娠や母になることのついて
困難も含めて見せたかった」と語り、
タリバンの支配する社会に
「女性たちは見えない存在になりたくないと思っている」
と話した。(朝日新聞2022年5月6日夕刊)
診療所前で娘が身に着けたブルカは「見えない存在」の象徴だったのか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ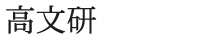
 関連書籍
関連書籍











