- NEWS
アジア新風土記(86)香港「雨傘革命」の挫折

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
2014年秋、香港の大通りは若者たちで溢れていた。
警察部隊の催涙弾、放水を雨傘で防ぎながら抵抗していた。
いつ壊れるかもしれない雨傘に次の雨傘が続き、若者たちは前に進んでいった。
遠くにトラム(2階建て路面電車)が見えた。
そのとき、台北にいた。
テレビに映る映像が香港だとは信じられなかった。
かつて暮らした街でも通りでもなかった。
それでもトラムを見て自分を納得させた。
9月28日、中国が行政長官選挙の候補者は親中派が多数を占める指名委員会の過半数の支持が必要だとしたことに抗議する学生、市民らが香港島中心部の中環(セントラル)などを占拠して警官部隊と衝突した。
中国政府の意に沿わない候補者が事実上排除されたことと警察当局の強引な対応に反対する人たちの支援は日を追って高まり、市街地の占拠は九龍半島にも広がっていった。
若者たちの武器はネットだった。
警察部隊の動きを察知、ネットを通じて逐一情報を流してゲリラ的に動き回った。
香港政府との話し合いも度々設けられたが、政府は行政長官選挙方式を撤回せず、中国外交部も「香港は中国の香港である」という趣旨の声明を発表するなど強硬姿勢に終始した。
香港島を中心に2か月以上続いた騒乱状態は最終的には12月15日の香港島・銅羅湾(トンローワン)での強制排除によって終息した。
若者たちの行動は最初、「革命」と呼ばれた。
そこには中国が返還時に約束した「一国二制度」の順守を求める強い意思、勢いがあった。
返還後50年間は保障された自由な社会では政府トップの行政長官は市民の気持ちが最大限反映されたシステムで選ばれるべきだという明確な主張があった。
「占拠地」から聞こえてくるのはミュージカル「レ・ミゼラブル」のなかで王制打倒に立ち上がった市民らが歌った「民衆の歌」だった。
広東語で口ずさむ人たちに去来していたものは何だったのか。
「雨傘革命」はいま「雨傘運動」と呼ばれるようになった。
なぜ「革命」は「運動」という言葉になったのか。
現状打破への試みが頓挫したことによって変わっていったのか。
理由はわからない。絶対的な中国政府に対してはまさに「蟷螂の斧」だった。
しかしそれでも、若者たちの行動はやはり「革命」であり、その「挫折」と呼ぶべきではないのか。
香港の若い人たちの熱気を肌で感じた時があった。
返還から15年を迎えた2012年7月1日の夜だった。
「自殺」と報じられた北京・天安門事件指導者の死の真相究明と新行政長官辞任を求めたデモ隊が香港島・西営盤の中国・駐香港特区連絡弁公室に向かった。
中国政府の意向を香港政府に伝え、様々な指示を下す拠点へのデモは「北京」への異議申し立てだった。
弁公室まで100メートルもない路地で、学生、サラリーマンらが警官隊と対峙していた。
車道と歩道を分ける柵に乗って声を張り上げ、歩道を埋めた人たちは、スコールのような突然の驟雨にも動かなかった。
返還記念日のデモはこれまでは昼間に行われ、夕方には終わっていた。
銅鑼湾(トンローワン)のビクトリア公園を出発、中環あたりで解散していた。
夜になっても散会しなかった若者らが香港島の最西部にある西営盤まで向かった行動は、整然としていた香港のデモを激しく予測不能のデモへと変質させた。
通りの一角で彼らのぎらぎらした目を追いながら、そんなことを考えていた。
香港社会は返還後、中国政府との蜜月時代が続いた。
亀裂のきっかけの一つは香港政府が12年9月から愛国主義を徹底させる「国民教育」の実施を打ち出したことだった。
授業での普通話の徹底は結果的に英語学習時間の短縮につながる。
香港と英語は植民地時代から切っても切れない関係にあり、香港が国際金融センターとして機能していく上での欠かすことのできないアイテムだった。
頭越しの愛国主義教育に生徒らが反発、子供たちの行動に親たちも英語教育の形骸化を恐れて支持するという空気が生まれた。
実施直前の7月29日の香港市街地での反対デモには子供連れの家族など主催団体の発表で9万人以上、警察発表でも3万人を超えた。
学生だった黄之鋒氏、周庭氏らは「学民思潮」という組織を立ち上げ、2年後の雨傘革命の中心になっていった。
中国政府に国民教育導入によって「必然的に中国を愛する国民が生まれるはずだ」という確信があったことは想像に難くない。
返還時に物心がつくかつかないかの幼児、あるいは返還後に生まれた子供たちが、十代、二十代の若者に成長して中国の政策に異を唱える動きを起こすなどとは想像もできなかったのではないか。
若者らのエネルギーは雨傘革命から5年経った19年の逃亡犯条例改正案反対運動でさらに爆発した。
この年も連絡弁公室周辺での抗議行動が起こった。
そのことへの怖れが国家安全維持法(国安法)の施行に繋がったのではないかという指摘もあった。
逃亡犯条例改正案反対運動の中で生まれた楽曲「香港に栄光あれ」は24年5月8日、高等法院(高裁)が演奏、ネット配信を禁じる命令を出す。
「顔を上げ沈黙を拒否しよう 叫びを響かせよう この地に自由が戻るように」といった歌詞の楽曲は高等法院が23年7月、表現の自由として認める判断を示していた。香港政府は不服を申し立て、高等法院は政府の意向を受け容れる形で1年前の判断を翻した。
市民らが拠り所とした自由への微かな希望も消えた。
(『アジア新風土記66』参照)
香港政府・警察当局の「監視体制」はすでに日常になった。
「香港に栄光あれ」禁止から1か月後の6月6日、サッカーワールドカップアジア2次予選の香港対イラン戦では観客3人が中国国歌斉唱時に起立しなかったり、グラウンドに背を向けたりしたとして国歌条例違反で逮捕された。会場にいた警官らが観衆の様子を撮影していたという。
香港を脱出してカナダに生活の拠点を移した民主派団体「香港衆志(デモシスト)の元幹部周庭氏は「普通に生きられて、普通に政府を批判でき、普通にデモに参加できて、普通にSNSで発信できるのは幸せなことだと思います」と話した。(朝日新聞 23年12月23日)
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ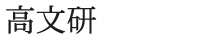
 関連書籍
関連書籍











