- NEWS
アジア新風土記(12)アフガン政権崩壊

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
1990年秋の北京アジア大会にアフガニスタンから24歳の若者が重量挙げ75キロ級に出場した。大会前は政府軍兵士として反政府ゲリラと戦っていた。東部ジャララバードではロケット弾も撃った。戦闘が止み、後方に引き上げてもまたすぐ前線に戻った。
自己ベストを40キロも下回っての9位は不本意だった。
「みんなが一緒になったらもっと強いチームができるはずだ。それでも・・・」と話した。
「この2週間は平和だった。砲弾の音もない」
若者は大会が終わって再び、戦火の故国に帰っていった。
31年が過ぎたいまに至るまで、アフガンに砲弾の音が聞こえないときはなかった。
2021年8月15日、イスラム主義勢力 タリバンが首都カブールの大統領府を占拠、アフガン政権は崩壊した。ガニ大統領は国外に脱出、カブール空港には国外に退避しようとする外国人、アフガン人が殺到した。
26日には空港近くでタリバンに敵対する過激派組織「イスラム国(IS)」支部組織「ISホラサン州」の自爆テロが起き、米兵13人を含む100人以上が殺された。「ホラサン」はイランからパキスタンにかけての地域を表す古称だ。
タリバンの2度目になる「国家」への道筋はまだ見えてこない。「敵」である米軍が去ってタリバン内の強硬派と穏健派の対立は激しくなるのか、各地の軍閥などとの協調はあるのか、「ISホラサン州」、潜伏しているとされる国際テロ組織アルカイダとの戦いは続くか。タリバンが米軍の掃討作戦にゲリラ活動で対抗したように、反対勢力がゲリラになるかもしれない。
何よりも国際社会の規範とどう折り合いをつけていくかという問題がある。厳格なイスラム原理主義は特に女性の社会進出、女子の学校教育に不寛容だ。「イスラム法が認める範囲」という制約はすでにテレビキャスター、銀行員らの職を奪い始めている。街には全身を包み込む衣装「ブルカ」を買い求める女性たちが急増している。
タリバンは全人口3900万人の4割を超える最大民族パシュトゥン人の神学生らを中心に結成され、1994年の南部カンダハル制圧後、98年9月にはほぼ全土を支配下に置いた。米国は2001年、米同時多発テロを起こしたアルカイダの本拠がアフガン国内にあるとして地上軍を派遣、12月にはタリバン政権を崩壊させる。タリバン後のアフガン政権は米軍の後ろ盾のもとにパシュトゥン、タジク、ウズベクなど各民族の均衡の上に続いた。
この20年のアフガンは民主社会へと歩み始めることができたのだろうか。教育面での成果をユニセフ(国連児童基金)の18年6月の報告書に見る。
15歳から24歳までの識字率は05年の31パーセントが17年には54パーセントになった。7歳から17歳までの約半数にあたる370万人がまだ未就学だが、男女の割合は4対6になった。わずかな進歩とも言えるが、その実りを得るまでに多くの人たちの血が流れた。
米ブラウン大がまとめた01年9月から19年11月までの民間人死者は4万3074人、アフガン軍・警察にタリバン兵士らを合わせれば14万9298人になる。(朝日新聞21年8月11日付け)
犠牲者は無機質な数字の羅列のように増え続ける。米軍が去ってこれからも毎日、何人もの人が死に、負傷し、行方不明になっていく。それでもアフガンの人たちにとっては故国に変わりはなかった。
米軍は8月30日、アフガンからの撤退の完了を表明、外国に軍隊を派遣する最も長い「戦争」は終わった。米軍将兵の死者は2300人を超えた。軍事経費は退役軍人支援などを含めて2兆2600億ドル(約250兆円)に上ったともいわれる。(米ブラウン大、アフガン支援NGO「カレーズの会」会報―アフガン事務所長シェルシャー・レシャード「現地活動レポート令和3年4~6月」)
米国内に戦争への厭世感は高まっていた。しかし、タリバンの猛攻と自爆テロによる米兵殺害はバイデン大統領の早期撤退戦略と情報分析の甘さへの批判を生んだ。無人機(ドローン)による自爆テロへの報復攻撃は新たな「戦争」の呼び水になる危険性を孕んでいる。
日本は02年に東京のアフガン復興支援国際会議で共同議長を務め、農業、各種インフラの整備から警察官養成まで約7000億円の支援を行ってきた。今後にどう繋げていくか。
旧タリバン政権は中央アジア、ロシア南部などへの浸透を狙うイスラム過激派の潜伏先だった。周辺国は「温床」の復活を恐れる。中国はタリバンとウイグル族の独立派組織「東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)」との協力関係には神経を尖らせざるを得ない。
アフガンはヒマラヤから伸びるヒンズークシ山脈が中央部の北東から南西にかけて連なり、国土の4分の3を占める。深い峡谷がその峰々を分断、南には砂漠、北には草原が広がっている。変化に富んだ地形は思わぬ光景を演出する。
赤茶けた砂塵が舞うだけの道はいつか谷に入り、谷底にはポプラの木々が茂り、オアシスは豊かな水で溢れ、鋤(すき)鍬(くわ)を持った男たちに出会う。中央山脈の峠道を北に下れば、その昔の汗血馬を思わせるような馬に乗った男たちに遭遇する。草原から突然姿を現し、アスファルト道路を横切ってまた草原の中に消えていく。
カブールからカンダハルに通ずる幹線道路を150キロほど行くと、10世紀から12世紀にかけて栄えたガズニ王朝の都だったガズニの街がある。私が立ち寄ったとき、一人の男が手招きして、はずれのモスクまで連れていった。待っていたのは数学の問題だった。.jpg)
先生のモッラー(イスラム神学者)と二人の少年が図形に取り組んでいた。教室、机のない砂礫の上での「授業」だった。モッラーが私にやれといった。砂漠の中で幾何の問いを突き付けられるとは想像もしなかった。
「わからない」を繰り返してなんとか解放してもらったが、翌日また行くと同じ先生、同じ生徒が同じ問題に向き合っていた。少年たちがわかるまで先へは進まないということだった。気の長い話に付き合いながら、ここでは昨日と今日のどこに違いがあるのだろうかと思い、答えが見つからなければ明日もまた同じなのだろうと、不思議に納得した。
アフガンにまだ国王がいて、それなりに治安が保たれていた1969年の話だ。アフガンにも心穏やかな時代があったことを記憶のどこかに留めておきたかった。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ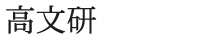
 関連書籍
関連書籍












