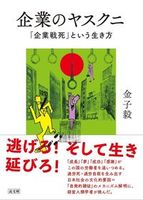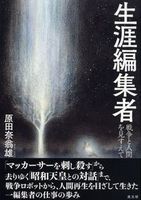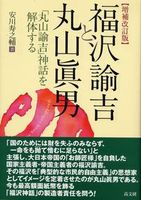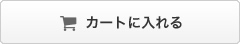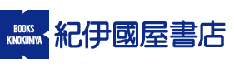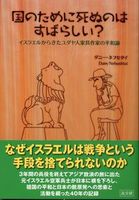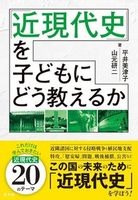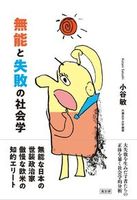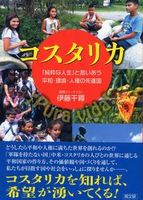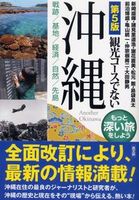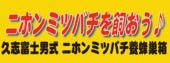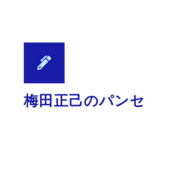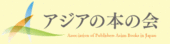アジア新風土記(98)フィリピン前大統領の「罪」 - 2025.03.31
「苦」をつくらない
サピエンス(凡夫)を超克するブッダの教え

差別・格差・貧困・・・これらの「苦」が充満する日本社会。
人々が「苦」をつくらないようにするにはどうしたらよいか?
解決のヒントはブッダの教えにあった。
ブッダは「苦」をつくり出す原因を「執着」にあると見定め、
「苦を取り除くために、執着する自己を見つめよ」と解いた。
電通の部長から村長になった異色の経歴をもつ著者が、
思索の末にたどり着いた「苦」を鎮めるブッダの処方箋を、
「執着」の最前線である「職場」や「政治・行政」の現場で活かせるよう提示する!
──「はじめに」にかえて
「無用の苦」に気づく
「苦の原因は、執着である」
ブッダ(釈尊)の教えの核心は「無我」
人々がつくりだす「苦」は増大している
序 論 ブッダ(釈尊)が発見したこと
ブッダ(釈尊)の生い立ち
無常=無我=縁起とは何か
なぜ「苦行は無意味」なのか
「本当の私」は存在しない
「凡夫の自覚」を遠ざける梵我一如型の思想38
釈尊の教えの全体構造
第1章 四諦 苦──この世は苦である
「執着の楽しみ」とは何か
「執着依存症」
動員された執着がもたらすもの
第2章 四諦 集──苦の原因は執着である
我執──執着の根元
仏教の梵我一如化──釈尊の教えからの逸脱
超越的原理への妄想を戒める
現代人のための「下準備」──自然へ身体を開く
わたしのジャッジメント──原発広告を断る
我執が組織化され、巨大システムが駆動する
第3章 四諦 滅──執着を滅すれば、苦の生産も止まる
「私」は執着の対象たり得るか
小さな反応の総体が「わたし」
執着を停止するために
第4章 四諦 道──執着を鎮めるためのプログラム
執着を鎮めるプログラム──三学と八正道
漢訳仏教用語の〝落とし穴〟
第5章 三学 戒──苦をつくらぬよう
自分という反応を整える
戒は完璧に守れるのか
自分が凡夫であることを自覚する
他力思想
「妙好人」の弱点──思考停止の危険性
「菩薩の自覚」の危険性──法華経信仰
プロパガンダ──執着が執着を操り動員する
熟議の民主主義への第一歩は「凡夫の自覚」から
第6章 三学 定 ──自分という反応を
ミニマムにしてしっかり観察する
基本は座禅
わたしは妄想だけでできている
観─自分という反応をつぶさに観察する
「無念無想」は役に立たない
第7章 三学 慧──自分のこととして
無常=無我=縁起を確認、納得する
無常、無我、縁起のよくある誤解
無常=無我=縁起とはどういうことか
「我思う、故に我あり」も思い込み
無我──「私」は妄想である
仏教学的な課題──釈尊の覚りは曖昧模糊たるもの?
十二支縁起について──「先に我あり」は人類共通の妄想
脳科学の視点から「無常=無我=縁起」を考えてみる
「我執=先に我あり」の起源
我執の生成・拡大のメカニズム
無常=無我=縁起であるのに努力できるのか
責任の問題
あとがき
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ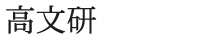

 関連書籍
関連書籍