- NEWS
徐京植評論集Ⅲ『日本リベラル派の頽落』「あとがき」より
その暗い地下室に入っていくと、部屋いっぱいに瓦礫が積み重なっていた。半ば瓦礫に埋もれるように、大きな球形の物体がある。よく見ると巨大な眼球だ。瞳に映った何かが蠢いている。それは幾種類もの核爆発のキノコ雲であった。暗い通路をたどって次の部屋に行くと、廃墟のような場所にタテ、ヨコ、ナナメにLED灯が赤く点っている。「国の交戦権は」「これを認めない」「陸海空軍その他の戦力は」「これを保持しない」……断片化された憲法九条の条文である。その場所は横浜市開港記念会館の地下。私は横浜トリエンナーレ美術展に来たのだ。作家は柳幸典である。
折からの台風。朝から各会場を回ってきた私の靴は水浸しだ。「この天候では投票率も上がらないだろうな」。その日は10月22日。「大義なき自己都合解散」による衆議院議員選挙の投票日だった。まさにそういう日に出遭うにふさわしい作品であったと言うべきか。
開票の結果は周知のとおり、与党の圧勝に終わった。安倍首相は早くも改憲(憲法への自衛隊明記)への動きを加速させると語った。野党は分裂の結果敗退した。わずかに急造の立憲民主党が健闘したが単独で改憲を阻止できる議席数には遠く及ばない。「希望の党」を名乗る右派ポピュリスト政党に合流する選択をした民進党は見事なまでに自壊した。
悪天候による低投票率や小選挙区制度の欠陥などもあるが、要するに多数の日本国民がそれを選択したのである。「モリカケ疑惑」や「アベノミクス批判」には答えないまま「北朝鮮の脅威」を叫び続けた安倍政権の戦略が功を奏した。結果として、日本の政界に「リベラル勢力」がほとんど存在しない状態になった。つまり「全体主義」の状態である。「リベラル派の頽落」が、とうとうこの水位にまで至ったのだ。
日本社会はここから立ち直って民主主義を再構築できるだろうか? それができなければ、未来は暗澹としている。戦争とファシズムの危機がますます迫ってくる。真っ先に犠牲になるのは在日朝鮮人など少数者(「内部の他者」)である。だが、犠牲はそこにとどまらないだろう。やがては「国民」多数も犠牲を免れることはできない。
ここで私は「再構築」「再建」という言葉を使ったが、そもそも「民主主義」が、内実を伴うものとして日本に存在していたかどうか疑わしい。こう書くと「自分は民主主義者だ」とか「自分は民主主義の諸価値を尊重している」とか主張して反発する人々が存在することは私も承知している。しかし、それは「民主主義」の消費者という意味ではないのか。決してその「生産者」(建設者)ではないのではないか。敗戦後、天皇制国家だった日本に戦勝国側から「民主主義」が供給された(「押し付けられた」)。その時、日本国民は「民主主義」の消費者となったが、生産者となることに失敗した。その貴重な「資源」を、あたかも化石燃料を大量消費するように自己中心的に消費し尽くした挙句に今日の惨状がある。
今後数年、日本の政治は「北朝鮮の脅威」「東京オリンピック」「天皇の譲位」というトピックを中心に動いていくだろう。これらの「政治的資源」を与党や支配層が自己の権益拡張のため徹底的に利用し尽くすだろう。異議を唱えるものは「非国民」扱いを受けて「排除」されることになる。必要とあれば「共謀罪」などを用いて弾圧もするだろうが、暴力的に排除する以前に国民多数は(リベラル派を含めて)「自粛」し「忖度」し、自発的隷従の度をますます深めていくだろう。全体主義の完成形態である。
昨年(2016年)、現天皇が譲位の希望を明らかにしてから、その法的根拠づけや手続きについてある程度議論が起きたが、そこに天皇制の廃止を唱える声はほとんど現れなかった。むしろ現天皇の「国民に寄り添う人柄」を称賛し、天皇制の存続を当然視する議論に覆いつくされている。安保法制反対などを主張するリベラル派の論客(内田樹)までもが、自分は「立憲デモクラシーと天皇制は両立しない」と考えていた時期もあったが、いまでは「天皇主義者に変わった」と宣言した(『朝日新聞』2017年6月20日)。国家には「政治指導者などの世俗的中心」とは別に、「宗教や文化を歴史的に継承する超越的で霊的な〈中心〉」があるほうがよい、それが天皇なのだ、というのである。
この議論に欠けている点は少なくとも二つある。過去の天皇制はまさしく天皇を「超越的で霊的な〈中心〉」に祭り上げ、それを軍部や政界が利用するというもたれ合いによって成り立っていた。天皇は「神聖にして不可侵」という明治憲法上の規定により天皇は戦争責任も問われないという理屈がまかり通っていた。最高責任者である天皇の責任が問われない以上、その命を受けた者たちの責任もまた問われることはない。為政者にとってこれほど好都合な仕組みはあるまい。
そのような構造は、天皇以外の人民が「自発的臣民」となることによってのみ成り立つ。日本は敗戦によってこの制度から抜け出し、日本人たちは臣民から市民へと自己を解放することができるはずであった。それなのに今、著名なリベラル派知識人が、みずからすすんで「臣民」の立場をえらぶというのだ。これはフランス革命以来、人類社会が積み上げてきた人権、平等、自由、民主といった普遍的価値にたいする破壊行為ではないか。
第二に、この議論に欠けていることは天皇制によって犠牲を強いられた人々──とくにアジアの戦争被害者の視点である。まさに天皇の「超越的霊性」という虚構によって、侵略と支配が遂行され、戦争責任は果たされないまま残ったのである。このことは本文中で強調したので、これ以上ここに繰り返さない。明らかなことは、この論者が少しも過去に学んでいないということだ。
「天皇制は何故やめなければならないか。理由は簡単である。天皇制は戦争の原因であったし、やめなければ、又戦争の原因となるかもしれないからである」
「馬鹿げた侵略戦争を世界中に仕掛けた以上、日本は世界に対してその責任をとらなければならない。天皇制と封建主義とが日本を好戦的にした根本的理由であるならば、その理由を除き、天皇制を廃し、封建的残滓を洗い、再び好戦的になり得ないことを実行を以て世界に示さなければならない」
ここに引いたのは日本敗戦直後1964年3月21日に東京大学『大学新聞』に掲載された「天皇制を論ず」という寄稿の一部である。筆者「荒井作之助」は、のちの評論家・加藤周一の筆名である。加藤周一は天皇個人と天皇制を区別して議論することの必要性を強調しながら、天皇制という制度の廃絶を主張しているのである。戦後間もない時期、日本の中にもこのような正論が芽生えていた。それが今では、ほとんど誰も天皇制の廃止を口に出さない社会になったのだ。
加藤周一は戦後日本を代表する知識人の一人である。「代表する」というのは、「戦後民主主義」という一時代の思想と精神をもっとも明瞭に体現する知識人であった、という意味である。侵略戦争と敗戦という失敗の経験を苦く噛みしめながら、今後の日本社会をよりよいものにしていこうとする精神、そのことを通じて「人間的」な普遍的価値を社会全体で実現していこうとする理想主義。その思想や精神は、敗戦後の廃墟に青々と芽吹いた草であった。
天皇制を温存した、植民地支配についての認識が欠如していた、などの多くの点で「戦後民主主義」は批判さるべき欠陥をもつものであったが、それでも戦前とは異なり、たとえタテマエとしてだけでも「人権」「民主主義」「平和」といった普遍的諸価値が掲げられた。このタテマエに内実を与えて、前記の欠陥を克服していくことが、戦後日本のリベラル派に課せられた責務となった。だが、今ではかつて日本に「戦後民主主義」という一時代があったと、過去形で語らなければならないのだ。だからといって、理想主義のかすかな光までも冷笑し、忘却してよいのか。この思いが、私に本書の筆を執らせた。
日本国民が今後、他者を再び害さず、自己も犠牲とならない道は、平和という目標を共有して被害諸民族と連帯することにしかない。国家と国家との「和解」ではない、日本の人と被害諸民族の人との「連帯」である。この連帯を阻んでいる最大の障壁は、日本における歴史修正主義であり国家主義である。
2017年10月25日
徐京植
折からの台風。朝から各会場を回ってきた私の靴は水浸しだ。「この天候では投票率も上がらないだろうな」。その日は10月22日。「大義なき自己都合解散」による衆議院議員選挙の投票日だった。まさにそういう日に出遭うにふさわしい作品であったと言うべきか。
開票の結果は周知のとおり、与党の圧勝に終わった。安倍首相は早くも改憲(憲法への自衛隊明記)への動きを加速させると語った。野党は分裂の結果敗退した。わずかに急造の立憲民主党が健闘したが単独で改憲を阻止できる議席数には遠く及ばない。「希望の党」を名乗る右派ポピュリスト政党に合流する選択をした民進党は見事なまでに自壊した。
悪天候による低投票率や小選挙区制度の欠陥などもあるが、要するに多数の日本国民がそれを選択したのである。「モリカケ疑惑」や「アベノミクス批判」には答えないまま「北朝鮮の脅威」を叫び続けた安倍政権の戦略が功を奏した。結果として、日本の政界に「リベラル勢力」がほとんど存在しない状態になった。つまり「全体主義」の状態である。「リベラル派の頽落」が、とうとうこの水位にまで至ったのだ。
日本社会はここから立ち直って民主主義を再構築できるだろうか? それができなければ、未来は暗澹としている。戦争とファシズムの危機がますます迫ってくる。真っ先に犠牲になるのは在日朝鮮人など少数者(「内部の他者」)である。だが、犠牲はそこにとどまらないだろう。やがては「国民」多数も犠牲を免れることはできない。
ここで私は「再構築」「再建」という言葉を使ったが、そもそも「民主主義」が、内実を伴うものとして日本に存在していたかどうか疑わしい。こう書くと「自分は民主主義者だ」とか「自分は民主主義の諸価値を尊重している」とか主張して反発する人々が存在することは私も承知している。しかし、それは「民主主義」の消費者という意味ではないのか。決してその「生産者」(建設者)ではないのではないか。敗戦後、天皇制国家だった日本に戦勝国側から「民主主義」が供給された(「押し付けられた」)。その時、日本国民は「民主主義」の消費者となったが、生産者となることに失敗した。その貴重な「資源」を、あたかも化石燃料を大量消費するように自己中心的に消費し尽くした挙句に今日の惨状がある。
今後数年、日本の政治は「北朝鮮の脅威」「東京オリンピック」「天皇の譲位」というトピックを中心に動いていくだろう。これらの「政治的資源」を与党や支配層が自己の権益拡張のため徹底的に利用し尽くすだろう。異議を唱えるものは「非国民」扱いを受けて「排除」されることになる。必要とあれば「共謀罪」などを用いて弾圧もするだろうが、暴力的に排除する以前に国民多数は(リベラル派を含めて)「自粛」し「忖度」し、自発的隷従の度をますます深めていくだろう。全体主義の完成形態である。
昨年(2016年)、現天皇が譲位の希望を明らかにしてから、その法的根拠づけや手続きについてある程度議論が起きたが、そこに天皇制の廃止を唱える声はほとんど現れなかった。むしろ現天皇の「国民に寄り添う人柄」を称賛し、天皇制の存続を当然視する議論に覆いつくされている。安保法制反対などを主張するリベラル派の論客(内田樹)までもが、自分は「立憲デモクラシーと天皇制は両立しない」と考えていた時期もあったが、いまでは「天皇主義者に変わった」と宣言した(『朝日新聞』2017年6月20日)。国家には「政治指導者などの世俗的中心」とは別に、「宗教や文化を歴史的に継承する超越的で霊的な〈中心〉」があるほうがよい、それが天皇なのだ、というのである。
この議論に欠けている点は少なくとも二つある。過去の天皇制はまさしく天皇を「超越的で霊的な〈中心〉」に祭り上げ、それを軍部や政界が利用するというもたれ合いによって成り立っていた。天皇は「神聖にして不可侵」という明治憲法上の規定により天皇は戦争責任も問われないという理屈がまかり通っていた。最高責任者である天皇の責任が問われない以上、その命を受けた者たちの責任もまた問われることはない。為政者にとってこれほど好都合な仕組みはあるまい。
そのような構造は、天皇以外の人民が「自発的臣民」となることによってのみ成り立つ。日本は敗戦によってこの制度から抜け出し、日本人たちは臣民から市民へと自己を解放することができるはずであった。それなのに今、著名なリベラル派知識人が、みずからすすんで「臣民」の立場をえらぶというのだ。これはフランス革命以来、人類社会が積み上げてきた人権、平等、自由、民主といった普遍的価値にたいする破壊行為ではないか。
第二に、この議論に欠けていることは天皇制によって犠牲を強いられた人々──とくにアジアの戦争被害者の視点である。まさに天皇の「超越的霊性」という虚構によって、侵略と支配が遂行され、戦争責任は果たされないまま残ったのである。このことは本文中で強調したので、これ以上ここに繰り返さない。明らかなことは、この論者が少しも過去に学んでいないということだ。
「天皇制は何故やめなければならないか。理由は簡単である。天皇制は戦争の原因であったし、やめなければ、又戦争の原因となるかもしれないからである」
「馬鹿げた侵略戦争を世界中に仕掛けた以上、日本は世界に対してその責任をとらなければならない。天皇制と封建主義とが日本を好戦的にした根本的理由であるならば、その理由を除き、天皇制を廃し、封建的残滓を洗い、再び好戦的になり得ないことを実行を以て世界に示さなければならない」
ここに引いたのは日本敗戦直後1964年3月21日に東京大学『大学新聞』に掲載された「天皇制を論ず」という寄稿の一部である。筆者「荒井作之助」は、のちの評論家・加藤周一の筆名である。加藤周一は天皇個人と天皇制を区別して議論することの必要性を強調しながら、天皇制という制度の廃絶を主張しているのである。戦後間もない時期、日本の中にもこのような正論が芽生えていた。それが今では、ほとんど誰も天皇制の廃止を口に出さない社会になったのだ。
加藤周一は戦後日本を代表する知識人の一人である。「代表する」というのは、「戦後民主主義」という一時代の思想と精神をもっとも明瞭に体現する知識人であった、という意味である。侵略戦争と敗戦という失敗の経験を苦く噛みしめながら、今後の日本社会をよりよいものにしていこうとする精神、そのことを通じて「人間的」な普遍的価値を社会全体で実現していこうとする理想主義。その思想や精神は、敗戦後の廃墟に青々と芽吹いた草であった。
天皇制を温存した、植民地支配についての認識が欠如していた、などの多くの点で「戦後民主主義」は批判さるべき欠陥をもつものであったが、それでも戦前とは異なり、たとえタテマエとしてだけでも「人権」「民主主義」「平和」といった普遍的諸価値が掲げられた。このタテマエに内実を与えて、前記の欠陥を克服していくことが、戦後日本のリベラル派に課せられた責務となった。だが、今ではかつて日本に「戦後民主主義」という一時代があったと、過去形で語らなければならないのだ。だからといって、理想主義のかすかな光までも冷笑し、忘却してよいのか。この思いが、私に本書の筆を執らせた。
日本国民が今後、他者を再び害さず、自己も犠牲とならない道は、平和という目標を共有して被害諸民族と連帯することにしかない。国家と国家との「和解」ではない、日本の人と被害諸民族の人との「連帯」である。この連帯を阻んでいる最大の障壁は、日本における歴史修正主義であり国家主義である。
2017年10月25日
徐京植
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ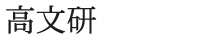
 関連書籍
関連書籍












