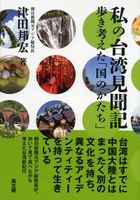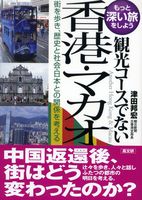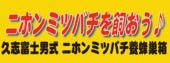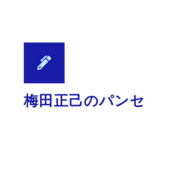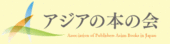- NEWS
アジア新風土記(99)韓国・尹大統領罷免

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
【動画】韓国の尹錫悦大統領を罷免 「非常戒厳」めぐり弾劾訴追https://t.co/siWgYqmAnE
— 朝日新聞デジタル速報席 (@asahicom) April 4, 2025
韓国の憲法裁判所は4日、国会に弾劾訴追された尹錫悦大統領に対し、「憲法秩序を侵害した」などとして裁判官の全員一致で罷免を宣告しました。
尹氏は失職し、60日以内に大統領選が行われます。 pic.twitter.com/lilukt21Qn
韓国の憲法裁判所は2025年4月4日、尹錫悦大統領の非常戒厳宣布の正当性を否定、憲法守護の観点から容認できない行為だとして罷免を宣告した。
裁判官全員一致の決定だった。尹大統領は24年12月3日夜に国政混乱を理由に非常戒厳を発したが、14日の国会の弾劾訴追案可決によって職務停止となっていた。尹大統領は失職、6月3日に大統領選が実施される。
憲法裁は非常戒厳について、尹大統領が主張する最大野党・共に民主党などの弾劾訴追による国政の機能不全は憲法上非常戒厳宣布が許される「戦時及びこれに準ずる国家非常事態」に当たらないと断じた。
軍、警察の国会などへの投入命令、政党活動などを禁止した布告令についても憲法違反を認める。
野党側の国会での権力乱用という訴えには「民主主義の原則に沿って解消しなければならない政治の問題だ」と指摘、野党側にも「対話と妥協を通じて結論を導き出すよう努力するべきだった」とした。
憲法裁の裁判官は現在8人で定員に1人欠ける。
各裁判官の考え方は保守2人、進歩(革新)3人、中道3人といわれていたが、全員一致による決定は裁判官各自の法に照らし合わせた判断であり、そこに法治国家を支える司法の独立をみたという指摘もある。
韓国憲法の「戦時に準ずる国家非常事態」は、北朝鮮と対峙しているという極めて特殊な環境下での条文ともいえる。
非常戒厳は一種のクーデターに他ならず、民主的手続きを経た大統領によって発せられたとしても、その試みは武力制圧と本質的に変わりはない。
尹大統領は罷免を受けて「国民の皆さんの期待に沿えず、あまりにも残念で申し訳ない」とのコメントを出した。
そこに「大それたことをした」という考えはないようにも感じられる。
大統領はクーデターという異常事態を起こすのは国軍に限ったことではないという「事実」を図らずも示してしまった。今回は「たまたま」失敗したという言い方もでき、将来に大きな禍根を残した。
非常戒厳から罷免宣告までの4か月間、韓国社会は弾劾支持派、大統領支持派に大きく分断された。憲法裁の決定当日、ソウル市内には両派の集会が開かれ、「民主主義の国で突然戒厳が宣布され、不安と怒りを感じた」「野党の妨害で無政府状態だった。戒厳は当然だ」といった声が報じられた。
司法判断が分かれなかったことで亀裂に歯止めがかかるかはわからない。大統領選までの2か月にどのような変化が起きるのだろうか。
24年12月3日深夜、大統領の非常戒厳をニュースで知った人々の最初の反応は、なぜいま、武力で体制を覆そうとする発想が生まれたのかということではないか。
民主化の道を確実に歩んでいるという思いが裏切られた瞬間だったのではないか。
その思いの先を作家、ハン・ガン(韓江)氏のスウェーデン・ストックホルムでの言葉で知る。
12月7日の『朝鮮日報』ウェブサイトはノーベル文学賞受賞記念記者懇談会での発言を
「願わくは、武力や弾圧で言路(上の人物に意見を述べる方法・手段)を阻むというやり方で統制する過去の状況に逆戻りしないよう、切に願っている」
と伝える。
韓国の人たちにとって「過去の状況」とは軍事独裁の時代であり、その時代を終わらせる転機が45年前の光州事件だった。1980年5月18日、朴正熙大統領暗殺事件後の軍事政権下、南西部・光州で民主化を訴える市民、学生らのデモ隊と空挺部隊が衝突、戒厳軍による掃討、鎮圧作戦は27日まで続いた。死者・不明者は240人以上といわれる。
武器を取って立ち向かった「市民軍」に街頭放送のアナウンサー役を務めた朴永順さんがいた。戒厳軍の急襲前、スピーカーから
「私たちは光州を死守します。みなさん、私たちを忘れないでください。私たちは最後まで闘います」
という最後の放送が流れる。
彼女は「もし市民が闘わずに道庁(全羅南道庁=筆者注)を明け渡していたら、民主化を求める運動は弱まり、今も軍事独裁政権が続いていたかもしれない。後悔はありません」と話した。(『朝日新聞』2022年7月14日夕刊)
ハン・ガン氏は光州で生まれ、9歳で故郷を離れる。事件はソウルに来て約4か月後に起きる。
事件を主題にした『少年が来る』(井手俊作訳、クオン、2016年)は、「雨がふりそうだ」という短い言葉で始まり、「君は声に出してつぶやく。ほんとに雨が降ってきたらどうしょう」と続いていく。
「君」は殺された人たちの遺体の収容作業を手伝う少年だ。
「君が腑に落ちなかったことの一つは、納棺を終えてから略式で行う短い追悼式で、遺族が愛国歌を歌うことだった。柩の上に必ず太極旗を広げ、紐でぐるぐるとくくり付けているのも変だと感じた。軍人が殺した人々にどうして愛国歌を歌ってあげるのだろうか。どうして太極旗で柩を包むのだろうか。まるで国が彼らを殺したのではないとでも言うみたいに」
『少年が来る』のエピローグは語る。
「特別に残忍な軍人がいたように、特別に消極的な軍人がいた。血を流している人を背負って病院の前に下ろし、急いで走り去った空輸部隊員がいた。集団発砲の命令が下されたとき、人に弾を当てないように銃身を上げて撃った兵士たちがいた。道庁前の遺体の前で隊列を整えて軍歌を合唱するとき、最後まで口をつぐんでいて、外信記者のカメラにその姿を捉えられた兵士がいた」
記念記者懇談会でも語りかける。
「若い警察官や軍人たちの態度も印象深かった。恐らく多くの方々が感じたと思うが、予期せぬ状況で何かを判断しようとし、内的な衝突を感じつつ、できる限り消極的に動いているという印象を受けた」「そのような(非常戒厳)命令を下した人々の立場からすれば消極的に見えただろうが、普遍的な価値の観点からすれば考え、判断し、苦痛を感じながらも解決策を見いだそうとした積極的な行為だったと思う」
ハン・ガン氏は「エピローグ」の言葉にどのような気持ちを込めたのか。記者懇談会の言葉にどのような思いを託したかったのか。 『少年が来る』
『少年が来る』
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ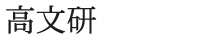
 関連書籍
関連書籍