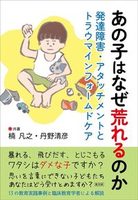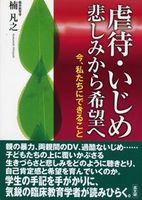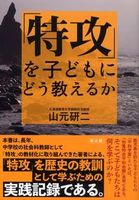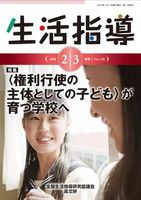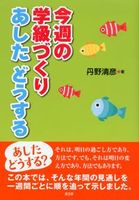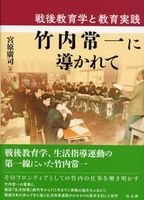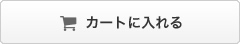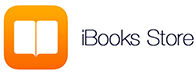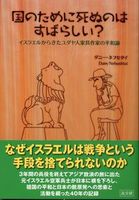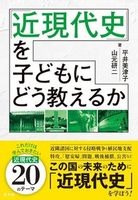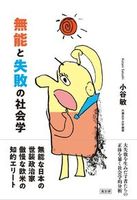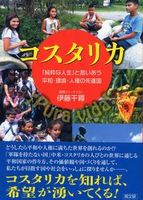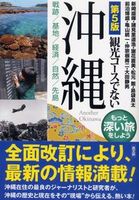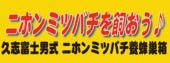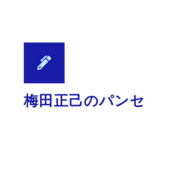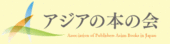アジア新風土記(95) 台湾・卑南遺跡 - 2025.02.14
自閉症スペクトラム障害の子どもへの発達援助と学級づくり (電子書籍)
現在、一クラスに三、四人はいると言われる発達障害(発達に困難を抱える)の子どもたち。その子たちとどう向き合い、その子たちも含めてどんな学級をつくっていくかは、担任の先生たちにとって大きな課題です。
教室で突然起こる暴力、パニック、止まない独り言や教室飛び出し……。そうした子は「困った子」ではなく、本当は「困っている子」であり、その「困っている子」たちの前にして、どんな取り組み(教育実践)が行われているか、数多くの事例を引きつつ、本来のあるべき教育のありようを描き出して見せてくれたのが本書です。
著書は繰り返し書いています。
「困難を抱える子どもたちの思いを大切にする取り組みは、同時に、教室にいる多くの子どもを大切にする。
特別な支援を必要とする子どもたちが安心して生活・学習できる環境は、すべての子どもたちが安心して生活・学習できる環境なのです」
教育現場が何かと困難な情況のなか、とりわけ発達障がいの児童を受け持つ教師や、特別支援学級の教師には必ず役に立つ本が出来ました!!
発達障害の子どもたちの問題で、はじめて本を作らせてもらったのは今から3年前の『ねえ! 聞かせてパニックのわけを』(篠崎純子・村瀬ゆい著)のときでした。不明にも、その時まで私は発達障害がどういうものであるのか、知りませんでした。
その時、著者のお二人が教えてくれたのは、「今や一クラスに発達障害、もしくはその周辺と思われる子どもは四、五人いる。私たちがこの本で伝えたいのは、発達障害の子どもへの個別の対応の仕方ではなく、そういう困っている子どもたちの困り感に寄り添いながら、学級ぐるみで、学級の子どもたちもいっしょに、その子たちを含め、ともに成長していける学級実践を探りたいし、ささやかだけれど、その取り組みを紹介したい」ということでした。
その『パニック……』の本はうれしいことに増刷になって、今も好評の一冊なのですが、今度、楠先生がまとめてくださった本書も、その狙いはまさにいっしょです。楠先生は繰り返し書いています。
「困難を抱える子どもたちの思いを大切にする取り組みは、同時に、教室にいる多くの子どもを大切にする。特別な支援を必要とする子どもたちが安心して生活・学習できる環境は、すべての子どもたちが安心して生活・学習できる環境なのです」と。
もう一点、本書で私自身とりわけ驚嘆したのは、楠先生が引用されている教育実践事例の豊富さです。
発達障害の子どもにどう向き合えばよいのか、どんな取り組みが子どもの発達を助けていくのか、実際の事例を複数つないで見せてくれると、そこに(1本の事例ではわからなかった)真実(教育の法則)が浮かび上がってきます。
紹介されている教育実践も、困難の中で今やここまで現場の先生たちが頑張って優れた実践を生み出しているのかと感動することばかりです。そういう意味でも、この本はきっと学校や学童保育の現場の先生たちの大切なバイブルとなってくれるだろうと思います。
〈1〉ASDの主要な特徴について
〈2〉障害の背後にあるASDの発達特性の問題
〈3〉ASDに対する不適切な対応によって生じる問題行動
Ⅰ章 子どもたちの自我・社会性の発達過程と自閉症スペクトラム障害
1節 就学前期の自我・社会性の発達過程と自閉症スペクトラム障害
2節 学齢期の自我・社会性の発達過程と自閉症スペクトラム障害
Ⅱ章 少年期の自閉症スペクトラム障害の子どもの発達権を保障する教育実践
1節 段階1(6~9歳頃)の発達権保障の課題と子ども集団づくり
2節 段階2(9~11歳頃)の発達権保障と子ども集団づくりの課題
3節 段階3(11~13歳頃)の発達権保障と子ども集団づくり
Ⅲ章 思春期の自閉症スペクトラム障害の子どもの発達権を保障する教育実践
1節 思春期の自閉症スペクトラム障害の子どもと歩む子ども集団づくり
2節 二次障害が深刻で支援が難しい子どもと子ども集団づくり
Ⅳ章 ASDの子どもを持つ保護者との共同・連携に向けての問題
〈1〉ASDの子どもを持つ保護者が体験してきた困難さや傷つき
〈2〉保護者との共同に向けての課題
〈3〉保護者にも発達障害の問題がある場合の対応
楠 凡之(くすのき ひろゆき)
1960年大阪生まれ。京都大学教育学研究科後期博士課程満期退学。北九州市立大学文学部教授。専門は臨床教育学、家族援助論。日本生活指導学会理事、全国生活指導研究協議会指名全国委員、日本学童保育学会理事、NPO法人学童保育協会理事長、学童保育指導員専門性研究会九州支部長。著書に『自閉症スペクトラム障害の子どもへの発達援助と学級づくり』(高文研)『いじめと児童虐待の臨床教育学』(ミネルヴァ書房)『気になる子ども 気になる保護者―理解と援助のために』(かもがわ出版)『気になる保護者とつながる援助』(かもがわ出版)他。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ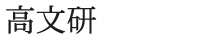

 関連書籍
関連書籍