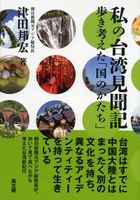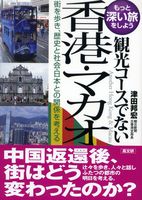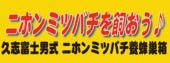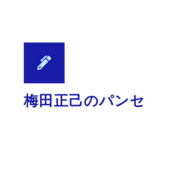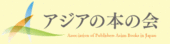- NEWS
アジア新風土記(95) 台湾・卑南遺跡

|
著者紹介 津田 邦宏(つだ・くにひろ) 1946年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。72年、朝日新聞社入社。香港支局長、アジア総局長(バンコク)を務める。著書に『観光コースでない香港・マカオ』『私の台湾見聞記』『沖縄処分―台湾引揚者の悲哀』(以上、高文研)『香港返還』(杉山書店)などがある。 |
卑南文化公園
台湾東南部は山も野も伸びやかだった。空は高く、明るい。
中央山脈は峻険な峰々が連なり、太平洋岸沿いには海岸山脈の穏やかな山並みがあった。
二つの山脈の合間に広がる大地と渓谷に五千年ほど前にはすでに先住の民が暮らしていた。
先住民卑南人の集落跡はいま卑南遺跡として知られる。
台湾鉄道の台東新駅は台東市街地から西北に約5キロのところにある。
駅舎の巨大な先住民像を見上げながら反対側に回ると、ほどなく「卑南文化公園」の看板が目に入った。
1980年、台東新駅と操車場の建設現場で1500個以上の石板棺が発見され、巨大な卑南遺跡の輪郭の一端が明らかになる。
青森県の三内丸山遺跡を連想する。三内丸山遺跡も東北新幹線・新青森駅が別の場所に建設されたならば、いまでも地中深く眠っていたかもしれない。
古代人の遺跡は多くは突然現われる。古代と現代を結ぶ糸というものが、人々の知恵といったものでは推し量ることの出来ない偶然の産物であることの不思議さに思いを巡らせながら歩いた。
台湾最大級の先史時代遺跡を訪れた日は快晴だった。
青空が眩しく、木々は生き生きと陽光を浴びていた。
総面積約80ヘクタールという敷地はあまりに広く、「遺跡」という概念を超えていた。
芝生の一角には卑南人の集会所を想定した高床式の建物があった。
細い木材で支えられた集会所は男性の通過儀礼として一緒に寝泊まりしたときに使われたと考えられている。日本の村落にあった「若者宿」のような役割を持っていたのかもしれない。
男子は12歳以上になると「集会場」に寝起きするという
考古現場の展示館には発掘当時そのままの石板棺がガラス張りの通路の下に並んでいた。
大きさは均一ではなく、みな同じ方向を向いていた。
形状もきちんとした箱型から一部が欠けているものなど様々だ。
石材のスレート(粘板岩)は薄く板状にはがれやすい性質を持ち、最適の材料だった。
翡翠のイヤリングや首飾り、陶製の瓶などの装飾品も同時に見つかっている。
斧、鎌などはすでに農耕を行っていたことを推測させた。
石板棺は身分によって大きさが異なった
月形石柱
展示館を出た後に出会った「月形石柱」という名の石柱は異様な形をしていた。
高さは約4・5メートル。先端が尖り、狼の咆哮を連想させた。
展示館の石柱レプリカが上部に円形の穴が開いており、月形石柱も風化によって穴が破損したとみられる。
最大の石柱のレプリカ。高さは4.85メートル
石柱群の本格的な調査は台湾を植民地とした日本の考古学者らによって始められた。
巨大石柱を最初にカメラに収めたのは1896(明治29)年に初めて台湾を訪れた鳥居龍蔵だった。
東部海岸の先住民の調査を行い、卑南遺跡に足を運んでいる。
石柱に関する記述は『鳥居龍蔵全集』(朝日新聞社、1976年)には見当たらなかった。
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館発行の『台湾世界を行く―鳥居龍蔵の見た海・山・ひと・ムラ―』(2024年)にも「アミ族の調査の後、山岳地帯に居住するタイヤル族やブヌン族とも接触し、最終的には台東の卑南を経て、プユマ族の居住する知本のムラを訪れている」とあるだけで、石柱の写真はなかった。
卑南遺跡の巨大石柱にはそれほどの興味を惹かれなかったのか。
日本人学者の業績が紹介されていた
鳥居の後も日本の考古学者らの卑南遺跡調査は続いた。
『台湾考古誌』(金関丈夫/国分直一、法政大学出版局、1979年)所収の「台湾東海岸卑南遺跡発掘報告」は太平洋戦争最中の1945年1月の調査報告だ。
空爆下、石柱の遺構は南北400メートル、東西100メートルの広がりをみせ、石柱の長軸方向は北東より南西に一直線となっていることを調べる。
同書は28年から数度調査した鹿野忠雄の報告も次のよう紹介している。
「此一帯の畑中にはスレートで出来たメンヒル(ヨーロッパ先史時代の直立した巨石記念物=筆者注)様の立石が数多遺っている。其の最大なるは一丈五尺(約4.5m=同)に及び又二間(約3.6m=同)、小なるもの一間位のものは数多ある」
石柱は土砂崩れなどで地上からほとんど姿を消し、月形石柱を残すだけだ。
遺跡周辺からのスレートの産出はなく、10キロ近く離れている中央山脈から搬出されたと考えられている。
用途としては建築資材説が鹿野の「往時の家の柱をなしていたと伝えられている」という報告などからも有力だが、台東市の台湾史前文化博物館ニュースレター『発現161号』(2009年8月15日)は、石柱の軸方向と切妻、梁の方向が一致せず、石柱が家の内部にあったとすると家屋が高くなり過ぎるとして、天体観測の可能性も示唆する。
先史時代の卑南人はどのような人たちだったのか。
台湾考古誌は台湾東海岸に限られた石柱遺跡の南限を卑南遺跡とし、住居址の構造から同じ先住民でも南部のパイワン族より北部のアミ族により類似性をみる。
「卑南」は別名「ピユマ」と呼ばれているが、台湾・中央通訊社日本語版『フォーカス台湾』は、2019年2月12日の特集で、遺跡の卑南人は現在のピユマ族とは別という説があると述べている。
東南アジア、南太平洋の人たちとの関連はどうなのか。
遺跡からはインドネシア系原住民族と同様の打製石鍬が出土しており(台湾考古誌)、先住民の話す「台湾諸語」は南太平洋を中心に1000種前後の言語を持つ「オーストロネシア語族」に属している。
18年にニュージーランド・マオリ族の少年少女がパイワン族を訪れるなど台湾と南太平洋地域の交流が盛んになっていることからも両者の近さが窺える。
台湾の歴史学者周婉窈氏は『図説 台湾の歴史』(濱島敦俊監訳、平凡社、2007年)で、オーストロネシア語族が台湾から拡散したというオーストラリアの学者の説を紹介する一方、別の学者グループは台湾先住民族の言語を古北インドネシア語の分枝としているとも書く。
そして「台湾が、オーストロネシア語族が東南アジアに拡散していく起点があったとすれば、数千年後に、いくつかのオーストロネシア語族が、再び台湾に戻ってきたことになる」と結んでいる。
鯉魚山頂から太平洋を望む
台東市内の台東旧駅西にある鯉魚山は海抜75メートルの小山だ。
山中から卑南人の石板棺が発見され、日本統治時代の台東神社は忠烈祠になっている。
参道裏は広葉樹の木々が繁茂して細い登山道が通じていた。
山頂からは台東の街並みと太平洋が見渡せた。風もなく海は静かだった。
遥か昔、古人は丸木舟で水平線の先へと漕ぎ出し、南の島々からの旅は台湾の地で終わったのか。
 ホーム
ホーム ご注文方法
ご注文方法 カートを見る
カートを見る お問い合わせ
お問い合わせ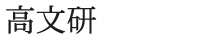
 関連書籍
関連書籍